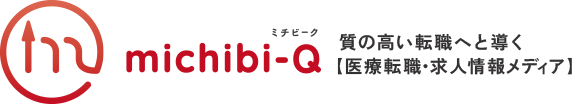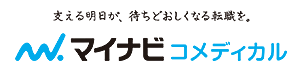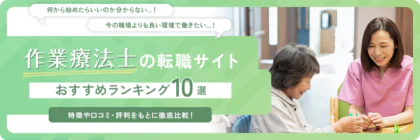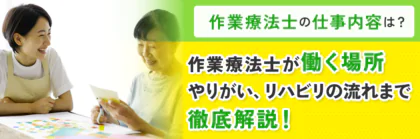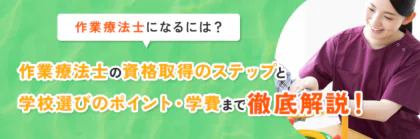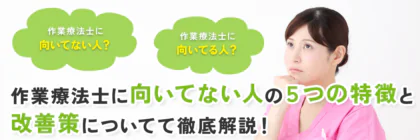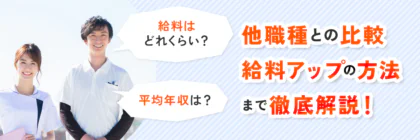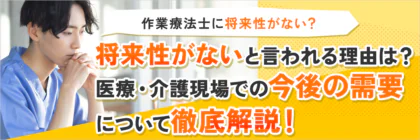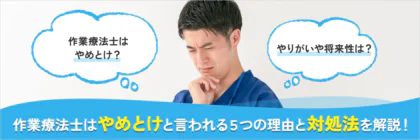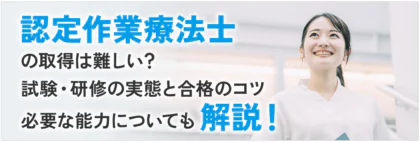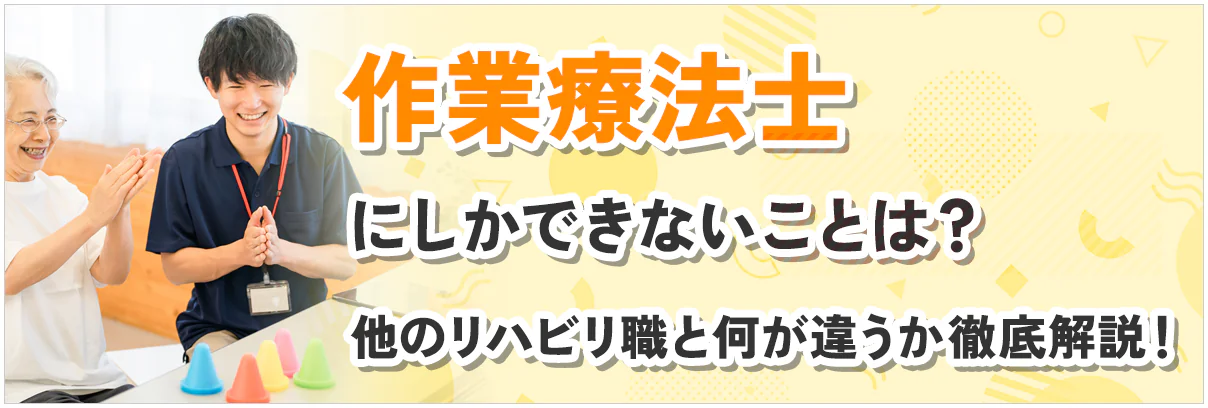
※当サイト(ミチビーク)はアフィリエイト広告を掲載しています。
この記事の目次を見る
- 1 作業療法士におすすめの 転職サイトランキング トップ3「ミチビーク調べ」
- 2 作業療法士にしかできないこと とは?
- 3 作業療法士にしかできないことを通して見える専門性とは?
- 4 作業療法士にしかできないことと他のリハビリ職の違いを わかりやすく比較
- 5 作業療法士にしかできないこと から見るリハビリの役割の 違いとは?
- 6 作業療法士にしかできないことが活かされる現場とは?
- 7 作業療法士に向いている人の特徴
- 8 作業療法士にしかできないことは将来どう変わる?他のリハビリ職との関係性もわかりやすく解説
- 9 作業療法士にしかできないことに関するよくある質問
- 10 まとめ|作業療法士にしかできないことをわかりやすく理解して 他のリハビリ職との違いを知ろう
- 11 作業療法士におすすめの 転職サイトランキング トップ3
作業療法士におすすめの
転職サイトランキング
トップ3「ミチビーク調べ」
さらに参考記事:作業療法士(OT)におすすめの2026年転職サイト・エージェント10選!転職に役立つ記事をご紹介!の記事もぜひご覧ください!
「作業療法士」という職業名は耳にしたことがあっても、実際にどんな仕事をしているのか、具体的に説明できる人は意外と少ないかもしれません。
さらに、理学療法士や言語聴覚士など、似たような名前の職種もある中で、「何が違うの?」と感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、作業療法士にしかできないことにフォーカスしながら、他のリハビリ職とどのような違いがあるのかをわかりやすく解説していきます。仕事内容だけでなく、働く現場や将来性、よくある疑問にも触れながら、作業療法士の専門性を丁寧にお伝えします。
作業療法士にしかできないこと
とは?
 作業療法士(Occupational Therapist:OT)は、医療や介護、福祉の現場で活躍する国家資格の専門職です。
作業療法士(Occupational Therapist:OT)は、医療や介護、福祉の現場で活躍する国家資格の専門職です。
リハビリの一種ではありますが、単なる「運動の訓練」ではなく、もっと広い意味での「生活の支援」を担っています。
ここでは、作業療法士だけが専門的に対応できるとされる主な5つの支援内容をご紹介します。
日常生活動作(ADL)の訓練を専門的に行う
作業療法士の代表的な業務のひとつが、ADL(日常生活動作)の支援です。
食事、更衣、トイレ、入浴といった「生きていくうえで欠かせない基本的な生活動作」を、自分の力でできるようにサポートしていきます。
もちろん理学療法士も動作訓練に関わりますが、作業療法士は「生活の中でその動きをどう活かすか?」という視点で訓練を組み立てます。
たとえば、服を着る動作ひとつとっても、使う手の動きや、立って着替えるか座って着替えるかといった判断は、その人の生活スタイルに合わせて個別に調整されます。
作業活動を通じて心身の回復を支援する
作業療法士は、単に体の動きや筋力を回復させるのではなく、「作業活動」という手段を通して心と体の両方にアプローチします。
ここで言う作業とは、掃除や洗濯、料理などの家事、手芸や園芸などの趣味活動、さらには就労に関する動作まで多岐にわたります。
このような活動を通じて、ただ身体機能を高めるのではなく、「できた」「楽しい」と感じられる体験を積み重ね、心の回復や自己肯定感の向上にもつなげていくのが作業療法士の特長です。
精神障害領域でのリハビリを担当できる
作業療法士は、リハビリ職の中でも唯一、精神科領域のリハビリテーションを正式に担うことができる資格です。
うつ病や統合失調症、発達障害、パニック障害など、さまざまな精神疾患を抱えた方に対して、生活リズムの構築や社会復帰に向けた支援を行います。
症状そのものに直接アプローチするのではなく、「朝起きて、着替えて、外に出る」といった日常生活を取り戻すためのリハビリが中心となります。
そのため、医師や心理士と連携しながら、生活支援の専門職として独自の役割を担っています。
自助具や生活環境の調整に携われる
日常生活で「できない」「やりにくい」と感じている動作に対して、道具や環境を工夫するのも作業療法士の重要な仕事です。
たとえば、握力が弱い方には持ちやすいスプーンを提案したり、片手で開けられるペットボトルキャップを選んだりと、その人に合わせた“ちょっとした工夫”で生活を支えます。
また、自宅での生活を安全にするために、手すりの設置や段差の解消といった住宅改修のアドバイスを行うこともあります。
こうした調整は、本人の自立を促すだけでなく、介護する家族の負担を軽減する効果もあります。
患者の「やりたいこと」を叶える支援ができる
作業療法士の支援で最も大切にされるのは、「その人がやりたいと思っていることを実現すること」です。
たとえば、「料理をまた作りたい」「孫と遊びたい」「もう一度働きたい」といった、本人の願いに沿った目標をリハビリの中心に据えるのが作業療法士の考え方です。
こうした支援を通じて、「できないことを補う」だけでなく、「その人らしい生活を取り戻す」ことを目指します。
ただの機能回復にとどまらず、“生きがい”に寄り添う支援ができる点が、作業療法士の魅力であり強みです。
作業療法士にしかできないことを通して見える専門性とは?
 作業療法士の仕事は「生活を支える」ことに特化していると言われますが、その背景には確かな専門性があります。
作業療法士の仕事は「生活を支える」ことに特化していると言われますが、その背景には確かな専門性があります。
ただ身体の動作を訓練するだけではない、深い理論と実践があるからこそ、作業療法士は他の職種とは異なる視点からリハビリにアプローチできるのです。
ここでは、そうした専門性がどのようなものかを掘り下げていきます。
作業科学に基づいた支援ができるから
作業療法士の支援には「作業科学(Occupational Science)」という学問が土台としてあります。
これは、人が日常的に行う「作業(activity)」が、どのように心や体、社会生活に影響を与えるのかを研究する比較的新しい分野です。
この理論に基づいて、作業療法士は「どんな作業がその人の回復につながるか?」を判断し、支援内容を設計します。
たとえば、ただ「歩く」よりも、「近所のスーパーに歩いて行く」方がその人のモチベーションにつながるなら、そこを目標に設定する。
一人ひとりに合わせて、“意味のある作業”をリハビリに取り入れることができる点に、作業療法士の専門性が表れます。
人の「生活」に焦点を当てたリハビリができるから
医療やリハビリの世界では、どうしても「身体機能の回復」や「症状の改善」が優先されがちです。
ですが、作業療法士はあくまで“その人の生活全体”を見据えて支援を行います。
入院中は立てるようになっても、家に帰ってからトイレが遠くて間に合わない、料理ができないといった問題が出てくることもあります。
作業療法士はそうした退院後の生活も想定し、「自宅でどう過ごせるか」「今後どんな支援が必要か」を一緒に考えます。
病院の中だけでなく、患者の“その後の暮らし”まで含めてリハビリを設計するのがOTの視点です。
身体と精神の両面をサポートできるから
もうひとつ、作業療法士の特徴として大きいのが、「心と体の両方に関われる」点です。
理学療法士は身体のリハビリ、言語聴覚士は言語や嚥下といった機能に特化していますが、作業療法士はこれらに加えて精神面への支援も含めてサポートします。
たとえば、脳卒中で片麻痺になった方が、意欲を失ってリハビリに取り組めないといったケースでは、身体の訓練だけでは回復が進みません。
そんなとき、作業療法士はまず「この人は何に楽しさを感じるのか」「何を大事にしているのか」といった心理的な側面から関わり、その人が前向きになれる作業を見つけてリハビリに活かします。
体が良くなっても心が動かないと生活は前に進みません。作業療法士はその両方に目を向け、バランスよく支援する数少ない職種なのです。
作業療法士にしかできないことと他のリハビリ職の違いを
わかりやすく比較
 リハビリ職とひと口に言っても、作業療法士・理学療法士・言語聴覚士・柔道整復師など、それぞれの専門分野は異なります。
リハビリ職とひと口に言っても、作業療法士・理学療法士・言語聴覚士・柔道整復師など、それぞれの専門分野は異なります。
ただ現場で連携することが多いぶん、仕事内容が似ているように見えることもあり、「何が違うの?」と感じる人も少なくありません。
作業療法士が他の職種とどう違うのか、わかりやすく比較していきます。
理学療法士との違いは「動作」か「生活」
理学療法士(PT)は、「座る・立つ・歩く」といった基本的な身体の動きを回復させることに特化しています。
手術や脳卒中の後遺症、運動機能の低下などに対して、筋力訓練や歩行練習などを通じて身体機能を高めるのが主な仕事です。
一方、作業療法士(OT)は、その動作を活かして「生活の中で何ができるか」を支援します。
たとえば、理学療法士が「歩けるようになる」ことを目指すなら、作業療法士は「歩いて買い物に行けるようになる」「トイレに自力で行けるようになる」ことを目指します。
“動けるようになる”のはゴールではなく、その動きで“生活ができるようになる”ことが作業療法士の役割です。
言語聴覚士との違いは「コミュニケーション」か「生活全体」
言語聴覚士(ST)は、「話す」「聞く」「飲み込む」など、言語と嚥下の機能に特化したリハビリを行う専門職です。
脳卒中後の失語症や構音障害、また高齢者の誤嚥防止などに対応します。
対して、作業療法士は、そうした機能を前提にしながら、「その機能を使ってどんな生活を送りたいか」に焦点を当てます。
たとえば、STが言葉を発する訓練を担当するなら、OTはその人が「店員に声をかけて買い物できるようになる」「友人と会話して楽しめるようになる」といった実生活の場面を想定した支援を行います。
STが「機能回復」の専門家であるのに対して、OTは「生活応用」の専門家と言えるでしょう。
柔道整復師との違いは「外傷処置」か「生活支援」
柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫などのケガに対して、整復(元の位置に戻すこと)や固定、テーピングといった処置を行う専門家です。
いわゆる「接骨院」「整骨院」で働いているイメージが強い職業です。
作業療法士は、ケガの治療そのものには関わりませんが、その後の生活復帰に向けた支援を行います。
たとえば、手首を骨折したあと、「再び包丁が握れるようになる」「仕事でパソコン作業ができるようになる」といった実生活での機能回復を支援するのが作業療法士の役割です。
つまり、柔道整復師はケガの“治し方”に特化し、作業療法士は“治ったあとどう暮らしていくか”に寄り添うという違いがあります。
作業療法士にしかできないこと
から見るリハビリの役割の
違いとは?
リハビリという言葉はひとくくりにされがちですが、実際には関わる職種ごとに役割が異なります。
それぞれが専門分野を持ちつつ、チームとして患者の回復と生活再建を支えているのです。
ここでは、理学療法士・言語聴覚士・作業療法士の役割の違いを、もう少し深掘りして解説していきます。
理学療法士は基本動作の回復が主な役割
理学療法士(PT)の仕事は、日常生活の土台となる「基本動作」を回復させることにあります。
たとえば、寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行など、私たちが無意識に行っている動作を「再びできるようにする」ことが専門です。
事故や病気で身体機能が低下してしまった場合、まずは動くことそのものが困難になります。
そのため、理学療法士は筋力トレーニングやバランス訓練、歩行練習などを通じて、身体の“基礎的な機能”を取り戻す支援を行います。
「体を動かすことそのもの」に特化しているのが理学療法士の役割です。
参考記事:理学療法士になるには?必要な学歴・資格の取り方や国家試験合格のためのポイントについて徹底解説!
言語聴覚士は言語・嚥下機能の改善が主な役割
言語聴覚士(ST)は、「話す」「聞く」「飲み込む」などの機能に特化した支援を行います。
たとえば、脳卒中で言葉が出にくくなった方、声がかすれて話しづらくなった方、高齢により食事中にむせやすくなった方などに対してリハビリを実施します。
コミュニケーションが難しい状態というのは、社会参加の大きなハードルになります。
また、嚥下障害は誤嚥性肺炎のリスクにも直結するため、命に関わる課題でもあります。
そのため、言語聴覚士はこうした「命と生活の質を守るためのリハビリ」に特化した専門職として欠かせない存在です。
作業療法士は生活の再構築が主な役割
作業療法士(OT)は、理学療法士や言語聴覚士の支援によって「動けるようになった」「話せるようになった」その先にある、“生活を取り戻す”ための支援を担います。
たとえば、料理がしたい、仕事に復帰したい、外出を楽しみたいなど、その人が送りたいと望む生活を一緒に描き、それを現実にしていくのが作業療法士の仕事です。
単に動作を練習するだけでなく、そこに「意味」や「目的」を持たせることで、モチベーションや生きがいにもつながります。また、生活環境の調整や、作業活動を通じた心のケアなど、身体だけではなく心と環境にも視点を向けるのが特徴です。
作業療法士は“生活全体”をデザインし、再構築する専門家として、多職種の中でも独自の存在感を持っています。
作業療法士にしかできないことが活かされる現場とは?
 作業療法士は、病院だけでなくさまざまな場所で活躍できる職種です。
作業療法士は、病院だけでなくさまざまな場所で活躍できる職種です。
その背景には、「人が生活する場すべてが作業療法の対象になる」という考え方があります。
ここでは、作業療法士の専門性が特に求められる現場を4つ取り上げてご紹介します。
病院やリハビリテーションセンター
作業療法士の最も基本的な活躍の場は、やはり病院やリハビリテーションセンターです。ここでは、脳卒中や骨折、神経難病、がんなど、身体に障害を持つ患者さんが退院後も自立して生活できるよう支援する役割を担っています。
たとえば、手がうまく動かなくなった患者さんが再び食事や着替えを自分でできるようにするために、食具の工夫や動作のトレーニングを行うのが作業療法士の仕事です。こうした「生活に直結した支援」を行うことが、理学療法士との大きな違いでもあります。
また、医療現場では医師、看護師、理学療法士、言語聴覚士など多職種と連携してチームで患者さんを支える場面が多く、チーム医療の一員としての役割も非常に重要です。
精神科病院やクリニック
作業療法士が精神科で果たす役割は非常に大きく、他のリハビリ職には代替できない部分です。
うつ病や統合失調症、発達障害、認知症など、精神的な不調を抱える方に対して、日常生活を取り戻すための支援を行います。たとえば、生活リズムの構築、人との関わり方の練習、家事の再習得など、症状に合わせた段階的なアプローチが求められます。
うつ病や統合失調症の方が社会に復帰するための支援として、集団活動や創作活動を通して生活リズムを整えるプログラムを提供します。
作業療法士はこうした支援を通じて、患者さんが社会と再びつながる第一歩を踏み出せるようサポートします。
介護老人保健施設(老健)
老健では、自宅復帰を目指す高齢者のリハビリを行う場として、作業療法士が中心的な役割を担っています。
日常生活に必要な動作の練習だけでなく、在宅での生活を想定した訓練やアドバイスも行います。
たとえば、トイレや入浴、更衣などの動作に不安がある方に対して、どのようにすれば自分でできるかを一緒に考え、必要に応じて道具や介助方法の提案も行います。
また、家族への助言やケアの指導も含めて、生活全体を支える視点が求められます。
訪問リハビリの現場
自宅で療養する方にとって、訪問リハビリは生活の質を左右する重要な支援のひとつです。
作業療法士は、実際の生活環境を見ながら、その場に合った支援を提供できるという強みを持っています。
自宅のキッチンで調理動作を確認したり、ベッドからトイレまでの移動を一緒に練習したりと、生活に直結したリハビリが行えるのは訪問ならでは。
また、環境調整の提案や、家族へのフォローアップも重要な仕事の一部です。
就労支援施設や福祉作業所
精神疾患や発達障害を持つ方が、就職や社会参加を目指すための支援施設では、作業療法士が活躍する場面が増えています。時間の管理、人とのコミュニケーション、集中力の維持といった働くうえで必要なスキルを、作業活動を通して養う支援を行います。
その人の特性や希望に応じて、適した職種の選択や職場環境への適応を一緒に考えることも重要な役割です。
発達障がいのある子どもに対しては、遊びを通して手指の動かし方や集中力、社会性を育てることを目的に、さまざまなプログラムを設計します。
たとえば、ブランコやボールなどを使って感覚の統合を促したり、工作を通して巧緻性(手の細かい動作能力)を育てたりする支援があります。学校生活に適応するための練習や、親御さんへの関わり方の助言も行います。
“できること”を見つけ、徐々に社会との接点を取り戻していく過程を支えるのが、作業療法士ならではの仕事です。
作業療法士に向いている人の特徴
作業療法士は「人の生活に深く関わりたい」という気持ちが強い人に向いている仕事です。一人ひとりに合わせた柔軟な支援が求められるため、観察力や創造力、そして共感する力も必要です。相手の小さな変化を喜びに感じられる人にとって、作業療法士は非常にやりがいのある職業です。
人の生活に寄り添いたい気持ちがある人
作業療法士の仕事は、単に「治す」のではなく、その人が自分らしく生活できるように「支える」ことに重きを置いています。ですから、目の前の人の話をじっくりと聞き、その人が何を大切にしているのか、どんな生活を望んでいるのかを理解しようとする姿勢がとても大切です。
「人の役に立ちたい」「困っている人を助けたい」といった思いが強い方は、作業療法士という仕事に大きなやりがいを感じることができるでしょう。単なる技術職ではなく、一人ひとりの人生や価値観に深く関わることが、この職業の本質です。
たとえば、ある高齢者が「もう一度自分で味噌汁を作って家族にふるまいたい」と話したとき、その気持ちを叶えるために環境や道具を工夫して実現する。そんな支援ができるのが作業療法士であり、人の思いに寄り添える人に向いていると言えるでしょう。
創造的な視点を持ち問題解決ができる人
作業療法士の支援は、マニュアルどおりに行えば正解というものではありません。同じ病気でも、その人の年齢、性格、家庭環境、趣味などによって、支援の方法は全く異なります。ですから、柔軟な発想力と観察力が必要です。
たとえば、手が不自由な方に「食事を楽しんでもらう」ためには、スプーンの形状を変えるだけでなく、姿勢の工夫や食事時間の調整、家族との協力体制など、多方面から問題を見つけて解決していく力が求められます。
アイデアを考えるのが好きな人、工夫することに楽しさを感じる人にとって、作業療法士は非常に魅力的な職業です。日々の仕事の中で、「できなかったことができるようになった」瞬間に立ち会える喜びは、何にも代えがたい経験です。
精神面のケアに関心がある人
作業療法士の大きな特徴の一つに、「こころのリハビリ」に関われることがあります。うつ病、不安障害、統合失調症など、精神的な悩みを持つ方に対して、作業を通じて自信や意欲を取り戻す支援を行います。
精神的な問題は目に見えにくく、アプローチが非常に繊細です。相手の言葉や態度の変化を丁寧に感じ取り、無理をせず、寄り添いながら支援する力が必要になります。そういった支援を根気強く続けるには、「人のこころの動き」に興味や関心を持ち、人の内面とじっくり向き合うことをいとわない性格が向いています。
精神科作業療法では、何気ない作業の中に大きな意味が込められていることも多く、相手の変化に気づき、小さな進歩を喜べる人が非常に適しています。
参考記事:作業療法士に向いてない人の5つの特徴と改善策について徹底解説!
作業療法士にしかできないことは将来どう変わる?他のリハビリ職との関係性もわかりやすく解説
高齢化社会の進行、医療の在宅化、そしてテクノロジーの進化。
これらの社会的な変化により、作業療法士の役割も着実に変化しつつあります。作業療法士の未来に起こり得る変化や、他職種との関係性の変化について考えていきます。
多職種連携が進むことで役割の明確化が進む
医療や福祉の現場では、もはや「1人の専門職がすべてを担当する」時代ではなくなっています。
理学療法士、言語聴覚士、看護師、介護士、ソーシャルワーカーなど、さまざまな専門家がチームで患者や利用者を支える「多職種連携」が当たり前になってきました。
この流れの中で、作業療法士の立ち位置もより明確に定義されつつあります。
「生活支援の専門家」として、身体機能のその先にある“日常”に対応するプロフェッショナルとして、チームの中で独自の役割を担うことが求められるようになってきました。
今後は、より細やかに役割分担が進み、OTの存在感はさらに高まることが予想されます。
地域包括ケアで作業療法士のニーズが増える
日本では、「病院から地域へ」という流れが加速しています。
これは「地域包括ケアシステム」と呼ばれるもので、高齢者ができる限り住み慣れた場所で、自分らしく暮らせるよう支援する仕組みです。
この考え方が進めば進むほど、「その人の生活を支えるプロ」である作業療法士のニーズは高まります。
病院の中ではもちろん、地域に出て、在宅生活を支える役割が今後ますます重要になるのです。
訪問リハビリ、地域活動支援センター、介護予防事業など、活躍の場は広がり続けています。
AIやロボットとの共存が求められる時代になる
テクノロジーの発展により、医療や介護の現場にもAIやロボットの導入が進んでいます。
すでに移乗支援ロボットや、自動で記録を取ってくれる介護AIなども現場に入ってきています。
しかし、どれだけ機械が便利になっても、「その人の想いをくみ取り、心に寄り添いながら生活を支える」という作業療法士の役割は、簡単に代替されるものではありません。
むしろ、AIやロボットをツールとしてうまく活用しながら、人にしかできない支援をより深めていくことが、これからの作業療法士に求められていくでしょう。
作業療法士にしかできないことに関するよくある質問
作業療法士という仕事に関心を持ったとき、具体的に「どこで働けるの?」「他の職種とどう違うの?」といった疑問が湧いてくる方も多いでしょう。
ここでは、そんなよくある質問を取り上げて、ひとつひとつ丁寧に解説していきます。
精神的な不調な人にも作業療法士は関わるのですか?
はい。うつ病や統合失調症、不安障害などの方に対して、「作業」を通じて社会復帰を支援するのは作業療法士の重要な役割のひとつです。理学療法士にはない専門領域です。
作業療法士は精神科だけで働けますか?
いいえ、精神科だけに限定された職業ではありません。たしかに精神科領域での専門性は高く、OTが唯一正式にリハビリとして関われる職種ではありますが、それだけが仕事のフィールドではないのです。
実際には、総合病院の整形外科や脳神経内科、介護施設、訪問リハビリ、小児発達支援、就労支援施設など、非常に幅広い分野で活躍しています。むしろ、精神科以外の現場の方が数は多く、作業療法士の強みは「どんな年齢・症状の人にも柔軟に対応できること」と言えるでしょう。
作業療法士と介護士の違いって何ですか?
作業療法士と介護士の大きな違いは、「何を目的として関わっているか」です。
介護士は、入浴や排泄、食事などの介助を直接行い、利用者の生活を “支える”ことが仕事です。
一方、作業療法士は、「どうすれば自分でできるようになるか」を考え、訓練や環境調整を通して“自立を促す”ことを目的に支援します。
たとえば、介護士がスプーンで食事を食べさせるとすれば、OTは「どうすれば自分でスプーンを持って食べられるか?」を考えます。
どちらも大切な役割ですが、援助するか、自立を引き出すかという視点に違いがあるのです。
作業療法士は子どもにも関わることができるの?
はい、もちろん関わることができます。
発達に課題のある子どもや、障害を抱える子どもに対して、作業療法士は遊びや生活動作を通じて支援を行っています。
具体的には、服を着る、靴を履く、筆記やハサミの使い方といった「手先の使い方」や「日常生活の習得」に関する訓練が中心です。また、集団活動への参加や、感情のコントロールを学ぶための支援など、社会性の発達をサポートすることもあります。
特別支援学校や療育センター、児童発達支援施設など、子どもの発達を支える現場にも作業療法士は必要とされています。
作業療法士が支援する対象者にはどのような人がいますか?
作業療法士は、脳卒中後の後遺症がある方、高齢者、精神疾患のある方、発達障害のある子どもなど、身体・精神・発達の分野を横断して幅広く支援します。
特に、病気やけがで日常生活に支障をきたしている方に対し、「その人らしい生活」を取り戻すためのサポートを行うのが作業療法士の重要な役割です。
作業療法士は在宅や訪問リハビリでも活躍していますか?
はい、作業療法士は病院や施設だけでなく、在宅医療や訪問リハビリの現場でも重要な役割を担っています。
利用者の住環境を実際に確認しながら、段差の解消や手すりの位置、福祉用具の提案など、生活に直結する支援が可能です。
自宅での「できること」を増やすことは、利用者のQOL(生活の質)向上にもつながります。
まとめ|作業療法士にしかできないことをわかりやすく理解して
他のリハビリ職との違いを知ろう
作業療法士の仕事は、「生活の再構築を支援すること」に集約されます。
ADL(日常生活動作)を回復させること、作業活動を通して心身の調子を整えること、精神障害のある人の生活リズムを整えること、さらには「その人が本当にやりたいこと」を叶える支援まで。
他のリハビリ職にはない、“暮らしの全体を支える”という独自の専門性を持っているのが作業療法士です。
また、精神科領域に正式に関われるリハビリ職であることや、身体と心の両面にアプローチできる点など、対応できるフィールドが広いことも特長のひとつです。
高齢社会や地域包括ケアの進展、テクノロジーとの共存など、社会全体が大きく変化していく中で、
作業療法士の「生活を見る力」「その人らしさに寄り添う力」は、これからさらに求められていくでしょう。
この記事を通じて、作業療法士にしかできないことや、他のリハビリ職との違いについて理解が深まったなら幸いです。
もし将来、リハビリや医療・福祉の分野での進路を考えるなら、作業療法士という選択肢もきっと魅力的に映るはずです。
作業療法士におすすめの
転職サイトランキング
トップ3
参考記事:作業療法士(OT)におすすめの2026年転職サイト・エージェント10選!転職に役立つ記事をご紹介!の記事はこちら
この記事の運営者情報
| メディア名 | ミチビーク |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社Method innovation |
| 会社ホームページ | https://www.method-innovation.co.jp/ |
| 所在地 |
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町3丁目6番11号 BADGE長堀BLD. 2階
|
| 代表取締役 | 清水 太一 |
| 設立 | 2016年11月1日 |
| 事業内容 | 集患支援事業 メディア運営事業 広告代理店事業 |
| お問い合わせ | michibi-Qのお問い合わせはこちら |