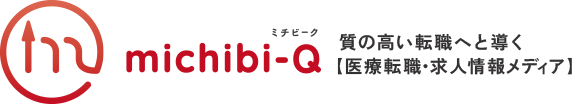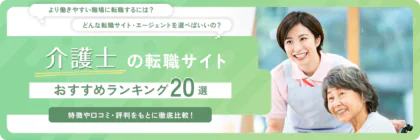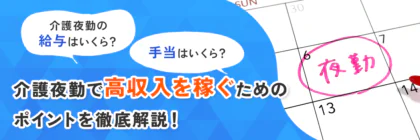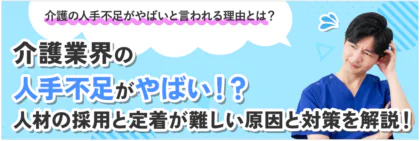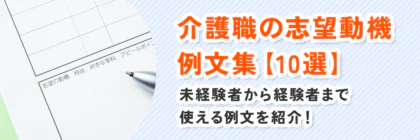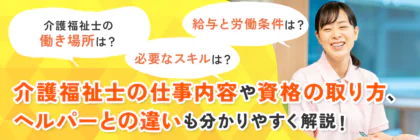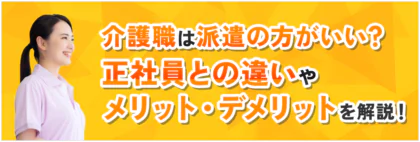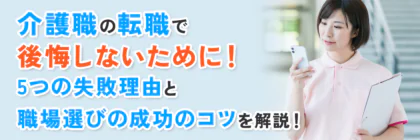※当サイト(ミチビーク)はアフィリエイト広告を掲載しています。
介護職におすすめの転職サイト
さらに参考記事:介護士のおすすめ転職サイト・エージェントランキング20選【2026年】評判・口コミも徹底解説!の記事もぜひご覧ください!
生活相談員は、高齢者や障がいのある方が介護施設などを利用する際に、相談対応や手続きのサポートを行う専門職です。利用者やその家族の心に寄り添い、安心して生活できるように支援する仕事として、介護業界の中でもとても重要な役割を担っています。
「どんな仕事をしているの?」「どんな人が向いているの?」「資格がないと無理?」など、生活相談員に関する疑問は多いですよね。
この記事では、生活相談員の仕事内容をはじめ、資格要件、給料、働ける施設の種類までをこれからこの仕事に関心を持つ方や、転職を検討している方にとって役立つ情報をわかりやすく解説します。
生活相談員とはどんな仕事?
仕事内容をわかりやすく解説
 生活相談員の仕事は、多くの人にとってあまり馴染みがないかもしれませんが、介護施設や福祉現場では非常に重要な存在です。この職種は、ただの「相談窓口」というだけでなく、利用者やその家族が安心してサービスを利用できるように支援し、施設内外の関係者と連携して介護の質を高める調整役でもあります。
生活相談員の仕事は、多くの人にとってあまり馴染みがないかもしれませんが、介護施設や福祉現場では非常に重要な存在です。この職種は、ただの「相談窓口」というだけでなく、利用者やその家族が安心してサービスを利用できるように支援し、施設内外の関係者と連携して介護の質を高める調整役でもあります。
利用者が自分らしい生活を送れるように、さまざまな面でサポートを行います。
利用者や家族の相談にのる仕事
生活相談員がまず担うのは、施設を利用する方やそのご家族との最初の接点となる相談対応です。たとえば「介護が必要になったが、どんな施設を選べばよいか分からない」「費用はどれくらいかかるのか」「どんな支援が受けられるのか」など、最初の段階で多くの疑問や不安が生まれます。
そうした相談に対して、生活相談員は専門的な知識と丁寧な説明をもとに、利用者にとって最適な選択ができるようにサポートします。また、利用後も困りごとがあれば随時対応し、必要に応じて他の職種(看護師や介護職など)と情報を共有しながら支援体制を整えるのも役目です。
介護サービスの利用手続きをサポートする
相談対応が終わり、利用希望者が入所を希望した場合には、生活相談員が手続きの案内と契約業務を行います。これは単に書類を渡して記入してもらうだけでなく、介護保険制度の説明や利用条件、料金の仕組みなども細かく説明する必要があります。
施設によっては、「入所判定会議」と呼ばれる内部会議に相談員が出席し、利用者の状態や受け入れの可否を判断する場面もあります。また、入所時には生活状況や健康状態を聞き取り、必要な支援内容を把握しておくことが後のケアに大きく関わります。
退所の際も同様に、家族やケアマネジャーと連絡を取り、スムーズな在宅復帰や転居ができるよう支援します。入所から退所まで、一貫して「橋渡し」をするのが相談員の役割です。
職員やケアマネジャーとの連携をとる
施設内での対応にとどまらず、生活相談員は地域の福祉機関や医療機関、行政窓口などとの調整役も担います。たとえば、利用者の急な体調悪化に伴う病院搬送の手配や、医療機関からの情報共有が必要になることがあります。また、福祉サービスの変更や介護保険の手続きなど、行政とのやり取りも日常業務の一部です。
さらに、ケアマネジャーや訪問介護事業所など外部との連携も密に行う必要があります。こうした調整をスムーズに行うには、的確な情報共有と信頼関係の構築が欠かせません。現場では「誰とでも話ができる力」や「関係をまとめる力」が自然と求められるのです。
生活相談員の仕事内容には
どんな役割があるの?
現場での実例も紹介
 生活相談員の仕事は多岐にわたります。施設の入り口から日々の生活まで、利用者の暮らし全体を支える存在です。
生活相談員の仕事は多岐にわたります。施設の入り口から日々の生活まで、利用者の暮らし全体を支える存在です。
具体的な業務の流れを知ることで、よりイメージしやすくなります。
新しく施設に入る人との面談をおこなう
新しい利用者が施設を利用する前に、生活相談員が本人や家族と面談を行います。体調や生活状況、希望するケア内容などを聞き取り、適切な対応ができるように情報を集めます。
この面談での印象が、利用者の安心感にもつながります。
サービス計画の作成に関わる
ケアマネジャーと連携して、利用者に合わせたサービス計画(ケアプラン)の作成にも関わります。生活相談員は、現場の情報や家族の要望を踏まえて、実現可能な内容を検討する役割があります。
より良い生活を提供するために、柔軟な提案が求められます。
トラブルが起きたときに仲介役になる
施設では、利用者同士や家族との間で意見の食い違いやトラブルが起こることもあります。そんなとき、生活相談員が冷静に話を聞き、間に入って調整します。
トラブルが長引かないように、迅速かつ丁寧な対応が求められる大切な役割です。
生活相談員の給料の相場と待遇の実情
 生活相談員として働く上で、やはり気になるのが「実際の給料はどのくらいなのか」「待遇にどんな差があるのか」といった点ではないでしょうか。このセクションでは、生活相談員の平均的な給与水準、手当や労働条件の傾向、そして雇用形態による違いについて、できるだけ分かりやすく解説します。
生活相談員として働く上で、やはり気になるのが「実際の給料はどのくらいなのか」「待遇にどんな差があるのか」といった点ではないでしょうか。このセクションでは、生活相談員の平均的な給与水準、手当や労働条件の傾向、そして雇用形態による違いについて、できるだけ分かりやすく解説します。
給与と昇給制度の傾向
生活相談員の年収は、全国的な平均で見るとおおよそ250万円〜400万円程度とされています。新卒や資格を取得したばかりの人は、年収250万円前後からのスタートとなることが多いですが、実務経験が3年以上ある場合には、年収300万円台に乗るケースも一般的です。
経験を重ね、主任やチームリーダーなどの役職に就くと、400万円を超える収入を得られることもあります。施設によっては人事評価制度や昇給制度が整備されており、毎年の評価に応じて月給や賞与が見直される仕組みも導入されています。
資格手当や各種手当の内容
相談員に支給される手当の中でも代表的なものが資格手当です。社会福祉士の資格を持っていれば、毎月5,000円〜10,000円程度が上乗せされることが多く、精神保健福祉士や介護支援専門員の資格でも同様に手当が付くことがあります。
そのほかにも、通勤手当・住宅手当・扶養手当など、職員の生活を支える各種手当が用意されている施設もあります。ただし、これらの手当の有無や金額は法人や地域によってばらつきがあるため、就職活動の際には求人票や面接でしっかり確認しておくことが大切です。
介護施設では、急な人手不足や業務の繁忙期には、残業や休日出勤が発生することがあります。また、夜勤がある施設では、体力的な負担が大きくなることもあるため、ワークライフバランスを考えながら勤務先を選ぶことが重要です。
労働時間や休日数の実態
生活相談員の勤務時間は、基本的には日勤帯(8:30〜17:30など)であることが多く、夜勤はほとんどありません。これは介護職と比べて大きなメリットの一つといえるでしょう。ただし、施設によってはシフト制を採用しており、早番や遅番が組まれる場合もあります。
休日については、週休2日制が一般的ですが、シフト勤務の施設では曜日が固定されないこともあります。また、年間休日数は法人の就業規則によって異なり、おおむね105日〜120日程度が目安です。施設によっては夏季・冬季休暇や有給休暇の取得状況にも違いがあるため、職場選びの際には事前に確認しておくことをおすすめします。
雇用形態別の年収・時給
生活相談員として働くには、正社員のほかに契約社員やパートといった雇用形態も選択できます。もちろん正社員が最も安定した収入と待遇を得やすいですが、家庭の事情などで短時間勤務を希望する人にとっては、パート勤務や短時間正職員という選択肢も魅力的です。
以下に、雇用形態ごとの年収・時給の目安を表にまとめました。
| 雇用形態 | 年収・時給目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 正社員 | 約280〜 400万円 |
昇給・賞与あり、社会保険完備 |
| 契約社員 | 約240〜 320万円 |
更新制、賞与はないまたは少額の場合あり |
| パート・ 非常勤 |
時給1,000〜1,500円程度 | 時間に応じた報酬、柔軟な勤務が可能 |
雇用形態によって待遇に差が出るため、自分のライフスタイルや今後の働き方に合わせて選ぶことが大切です。
生活相談員のやりがいとは?
仕事を通じて得られる喜び
生活相談員の仕事は、直接的に人と関わるため、大変なこともありますが、それ以上にやりがいを感じられる場面が多くあります。
「ありがとう」と感謝される場面が多い
生活相談員は、利用者や家族から直接「ありがとう」と言われることが多い職種です。相談にのって安心させたり、問題を解決できたときには、大きな感謝の言葉をもらえることもあります。
その一言が、毎日の仕事の原動力になります。
困っている人の助けになれる
生活に困っている方、不安を抱えている家族に寄り添い、少しでも心が軽くなるよう支えるのが生活相談員の仕事です。悩んでいる人の力になれるという実感が、やりがいに直結します。
人とのつながりを深く感じられる
相談員として働く中で、利用者や家族、職員との信頼関係が生まれます。相手の気持ちを理解し、支え合うことで、人と人とのつながりの大切さを実感できるのも、この仕事の魅力です。
生活相談員に向いている人の
特徴とは?適性をチェックしよう
 生活相談員は、人と関わる時間がとても多い仕事です。自分の性格や得意なことと照らし合わせて、向いているかどうかを見てみましょう。
生活相談員は、人と関わる時間がとても多い仕事です。自分の性格や得意なことと照らし合わせて、向いているかどうかを見てみましょう。
人と話すことが好きな人
利用者やその家族、職員など、さまざまな人と話す機会が多いため、人と話すことが苦にならない人に向いています。明るく丁寧な対応ができると、さらに好印象です。
気配りができる人
小さな変化や表情に気づく「気配り力」が、生活相談員には欠かせません。相手が何を感じているかを察知して、先回りして動ける人は、相談員として重宝されます。
相手の気持ちに寄りそえる人
ただ話を聞くだけではなく、相手の立場になって考え、心から寄り添う姿勢が必要です。共感力のある人は、利用者や家族から信頼されやすいです。
生活相談員になるにはどうすればいい?必要な資格や経験を解説
生活相談員になるためには、施設の種類や自治体の方針によって条件が異なる場合がありますが、いくつかの資格や経験があると有利になります。
社会福祉士・介護福祉士などの資格があると有利
多くの施設では、生活相談員の要件として「社会福祉士」「介護福祉士」などの資格が求められる場合があります。これらの資格は、専門的な知識をもって相談業務を行うために有利です。
特に社会福祉士は、相談支援の専門職としての評価が高いため、取得しておくと採用の幅が広がります。
社会福祉士と社会福祉主事任用資格の違い
生活相談員になるために最もよく求められる資格が、「社会福祉士」と「社会福祉主事任用資格」です。どちらも福祉に関する知識を持つことの証明になりますが、性格や取得方法が異なります。
社会福祉士は国家資格で、大学や専門学校で福祉を専門的に学び、国家試験に合格することで取得できます。医療機関や行政、施設など幅広い分野での活躍が期待され、相談業務のプロフェッショナルともいえる資格です。
一方で社会福祉主事任用資格は、大学などで所定の科目(社会福祉学、心理学、社会学など)を履修すれば得られる「任用資格」です。国家試験は不要で、学歴で取得可能な場合が多く、社会福祉士に比べて取得のハードルがやや低めです。
介護支援専門員など他資格との関係性
生活相談員としての採用においては、自治体や施設によって、介護支援専門員(ケアマネジャー)や精神保健福祉士などの資格を持っている人を認める場合もあります。これは、職務内容が相談業務や調整業務であるため、それに見合う専門性を持っていれば柔軟に対応できるという判断によるものです。
とくに、地域包括支援センターなどで働く場合には、複数の資格を持っていることが評価され、相談員業務に限らず、地域福祉全般に関わる業務を担当するチャンスが広がることもあります。
実務経験が必要な場合もある
一部の施設では、相談員としての実務経験、もしくは介護現場での経験が必要とされることもあります。そのため、未経験から生活相談員を目指す場合は、介護職として数年働いたのち、相談員にキャリアチェンジするケースも多いです。
現場経験があることで、利用者の気持ちや職員の立場がよくわかる相談員になれます。
自治体によって要件が違う場合がある
生活相談員の要件は、都道府県や市区町村によって異なる場合があります。施設ごとに独自の基準を設けているところもあるため、就職を考えている地域の条件を確認することが大切です。
ハローワークや福祉系の求人サイトで、詳しい要件を調べてみましょう。
生活相談員の勤務先は?
施設ごとの仕事内容の違いも紹介
 生活相談員が働く場所は、特別養護老人ホーム、デイサービス、病院などさまざまです。施設によって仕事内容にも違いがあるため、自分に合った職場を選ぶことがポイントです。
生活相談員が働く場所は、特別養護老人ホーム、デイサービス、病院などさまざまです。施設によって仕事内容にも違いがあるため、自分に合った職場を選ぶことがポイントです。
特別養護老人ホームでの仕事内容
特別養護老人ホーム(特養)は、要介護度の高い高齢者が長期的に入所して生活する施設です。ここでの生活相談員は、入所前の相談や手続きに加えて、入所後も継続的に利用者や家族と関わり、施設での生活が円滑に進むようにサポートします。
利用者一人ひとりの状態に合わせて、看護師や介護職員、ケアマネジャーと連携しながら支援を行う必要があり、チームでの情報共有や調整能力が特に重要になります。また、医療的な対応が求められるケースも多いため、医療機関との連携が必要になることも珍しくありません。
デイサービスにおける日常業務
デイサービスは、要介護・要支援の高齢者が日中のみ施設に通い、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受ける「通所型」の介護サービスです。生活相談員の業務としては、契約対応や利用開始までの調整、利用者の状態把握、日常的な相談対応などが中心です。
デイサービスでは利用者と接する時間が長く、施設内での様子を直接観察することができるため、家族へのフィードバックやケアマネジャーとの情報共有がしやすいというメリットがあります。毎日通ってくる利用者との距離が近いぶん、信頼関係の構築も業務の一環となります。
地域包括支援センターでの相談業務
地域包括支援センターは、高齢者の介護・医療・福祉・保健に関する総合的な相談窓口として各市町村に設置されています。生活相談員は、ここで「主任介護支援専門員」「保健師」「社会福祉士」とチームを組み、地域の高齢者が安心して暮らせるように支援します。
業務内容は施設での相談業務よりも幅広く、虐待の対応や認知症への支援、介護予防の啓発活動なども含まれます。行政との連携や地域住民とのつながりが強くなるため、施設勤務とはまた異なる視点での相談力と行動力が求められる職場です。
職場ごとのチーム構成と人間関係
生活相談員は基本的に「一人で何でもこなす」職種ではありません。むしろ、施設によっては看護職、介護職、ケアマネジャー、栄養士、機能訓練指導員など、多職種とチームで働くことが前提となります。
たとえば、特別養護老人ホームでは24時間体制のケアが必要となるため、職種間の連携が非常に重要です。デイサービスでは、少人数での運営が多いため、一人が複数の業務を兼務することも珍しくありません。地域包括支援センターでは、外部との関係構築や調整力がより強く求められる傾向にあります。
このように、働く場所によって求められる能力や業務範囲が大きく変わるため、自分の性格やスキル、将来像に合った職場を選ぶことが、長く安心して働くための鍵となります。
生活相談員のキャリアパスとは?将来の働き方を考える
生活相談員として経験を積むことで、将来的にはさまざまなキャリアアップの道が広がります。長期的な目標を持って働くことで、やりがいも大きくなります。
管理職や施設長を目指せる
施設によっては、生活相談員からスタートして、主任、管理者、さらには施設長へとキャリアアップする道があります。相談業務だけでなく、施設全体のマネジメントや職員の育成なども担うようになります。
実績や信頼を積み重ねれば、リーダーとしての活躍も可能です。
ケアマネジャーとして働く道もある
介護福祉士や相談員としての経験を活かして、ケアマネジャーの資格を取得し、ケアプラン作成の専門家として働く人も多いです。利用者の生活全体を支えるという点で、生活相談員との共通点も多い職種です。
現場経験が豊富な相談員は、より実践的なケアプランが作れると評価されています。
地域包括支援センターで活躍することもできる
高齢者の総合相談窓口である「地域包括支援センター」では、生活相談員の経験がある人材が求められています。地域全体の高齢者を支える重要な拠点として、幅広い相談に対応することが求められます。
行政や地域資源との連携も多く、より広い視点で支援に関わることができます。
生活相談員に関するよくある質問
ここでは、生活相談員を目指す方がよく抱く疑問について、わかりやすくお答えします。
生活相談員はどんな資格が必要ですか?
多くの施設では、社会福祉士や介護福祉士などの国家資格が推奨または必須とされています。ただし、無資格でも実務経験があれば応募可能な場合もあるため、求人情報をよく確認することが大切です。
自治体によって基準が異なるため、事前にチェックしましょう。
未経験でもなれますか?
はい、未経験から生活相談員を目指すことは可能です。特に、介護職からステップアップする形で転職する方が多くいます。最初は介護職として現場を知ることも、将来の相談員としての強みになります。
意欲や人柄が評価されるケースも多いので、まずはチャレンジしてみることが大切です。
生活相談員の仕事内容は介護職とどう違うのですか?
介護職は主に身体介助や生活支援を行う一方で、生活相談員は利用者や家族の相談に応じ、施設の調整役を担います。入退所の手続き、サービス内容の説明、他職種や外部機関との連絡調整が主な業務で、施設の「顔」としての役割も担っています。
人見知りでもできる仕事ですか?
人と関わる機会が多いため、最初は不安に感じるかもしれませんが、慣れてくると自然とコミュニケーションが取れるようになります。聞き上手な人や、じっくり相手の話を聞ける人は、人見知りでも信頼される相談員になれます。
明るく元気である必要はなく、誠実な対応が一番大切です。
生活相談員が働ける施設にはどんな種類がありますか?
主に「特別養護老人ホーム」「有料老人ホーム」「デイサービス」「地域包括支援センター」などがあります。施設の種類によって業務の幅やチーム体制が異なりますので、自分のスタイルに合った職場選びが大切です。
まとめ
最後に、生活相談員という仕事の魅力や特徴を振り返ってまとめます。
生活相談員は利用者の心の支えになる仕事
利用者や家族の悩みに寄り添い、安心して介護サービスを利用できるようにサポートするのが生活相談員の役割です。困っている人にとって、心の支えとなる大切な存在です。
人の役に立てるやりがいがある
感謝の言葉を直接もらえることが多く、人のために働いているという実感を得やすい職種です。日々の小さな対応が、誰かの生活を大きく支える力になります。
人とのコミュニケーションが大切な仕事
さまざまな立場の人と関わる生活相談員には、信頼関係を築く力が求められます。人との関係を大切にし、相手に寄り添える気持ちを持つ人には、とてもやりがいのある仕事です。
介護職におすすめの転職サイト
さらに参考記事:介護士のおすすめ転職サイト・エージェントランキング20選【2026年】評判・口コミも徹底解説!の記事もぜひご覧ください!
この記事の運営者情報
| メディア名 | ミチビーク |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社Method innovation |
| 会社ホームページ | https://www.method-innovation.co.jp/ |
| 所在地 |
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町3丁目6番11号 BADGE長堀BLD. 2階
|
| 代表取締役 | 清水 太一 |
| 設立 | 2016年11月1日 |
| 事業内容 | 集患支援事業 メディア運営事業 広告代理店事業 |
| お問い合わせ | michibi-Qのお問い合わせはこちら |