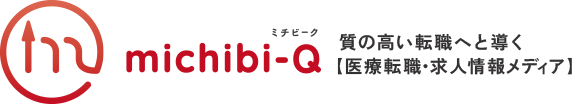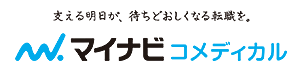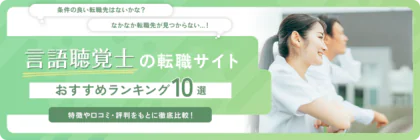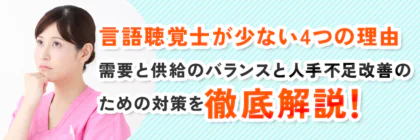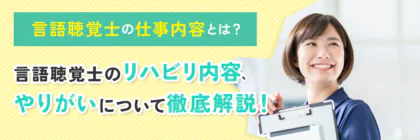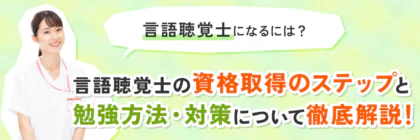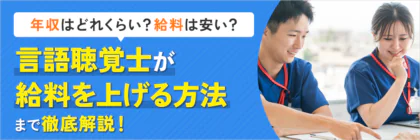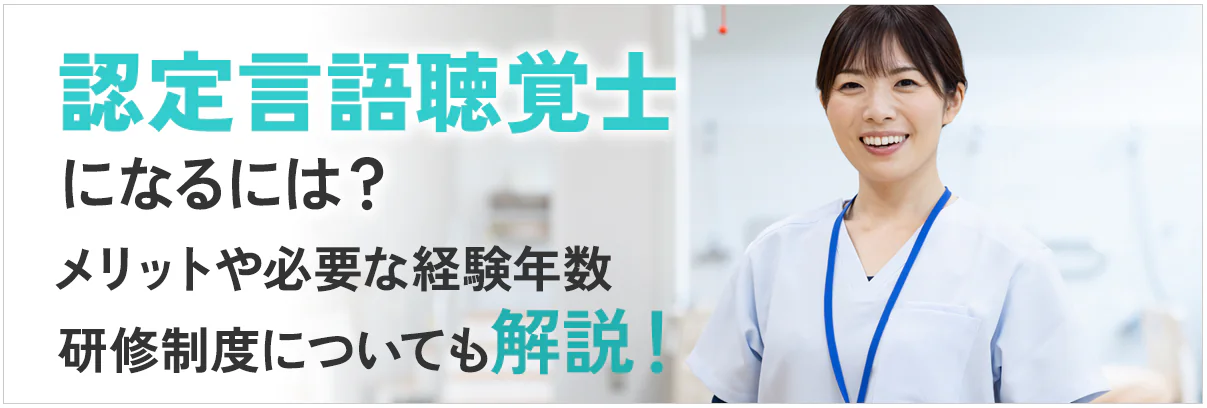
※当サイト(ミチビーク)はアフィリエイト広告を掲載しています。
言語聴覚士におすすめの
転職サイトランキング
トップ3「ミチビーク調べ」
さらに参考記事:言語聴覚士(ST)におすすめの転職サイト・エージェント10選をランキング形式で一挙紹介!の記事もぜひご覧ください!
「言語聴覚士としてもっと専門性を高めたい」
「臨床経験を活かして、次のステップに進みたい」
そう考えたとき、選択肢として浮かぶのが「認定言語聴覚士」という資格です。
しかし、「どんな経験が必要?」「どうやって取るの?」「取った後に何が変わるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、認定言語聴覚士になるための条件や流れ、必要な経験年数・研修制度・分野別の認定内容などをわかりやすく解説します。
キャリアアップや将来の働き方を見据えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
認定言語聴覚士とは何か?
基本的な概要を解説
 認定言語聴覚士とは、言語聴覚士(ST)としての国家資格を持ちながら、さらに特定の専門領域において高度な知識と技術を備えたスペシャリストに与えられる民間資格です。
認定言語聴覚士とは、言語聴覚士(ST)としての国家資格を持ちながら、さらに特定の専門領域において高度な知識と技術を備えたスペシャリストに与えられる民間資格です。
この資格は、日本言語聴覚士協会が2008年から運用しており、摂食嚥下障害や失語症、高次脳機能障害、発達障害、聴覚障害など、複数の専門領域に分かれた認定制度になっています。
専門性を深める資格としての位置づけを理解し、自身のキャリアにどう結びつくのかを明確にするための土台を築くパートです。
日本言語聴覚士協会が認定する専門資格
認定言語聴覚士の制度は、公益社団法人 日本言語聴覚士協会が公式に認定する資格制度です。
制度自体は比較的新しいものですが、全国的に統一された基準で認定が行われており、資格を取得すればどこでも通用する「専門家としての証明」になります。
臨床経験に基づいた専門性を証明できる資格
認定言語聴覚士は、机上の知識ではなく、実際の臨床経験と実績に裏打ちされた専門性を認定する資格です。
単なる勉強だけでは取得できず、一定の年数の実務経験や、現場での症例報告の蓄積が必要です。
「この分野について、深く理解し、質の高い支援ができる人材」として、第三者に証明できるのが大きな強みです。
複数の専門分野から選んで取得できる資格
認定言語聴覚士の資格は、「失語」「摂食嚥下」「構音障害」「小児コミュニケーション」「認知症」など、分野ごとに分かれています。
自分の興味や強みに合わせて分野を選べるのが特長で、将来的に複数の分野を取得することも可能です。
それぞれの領域で求められる知識や技術が異なるため、自分がどの領域でプロフェッショナルを目指したいかを明確にする第一歩にもなります。
言語聴覚士との違いと役割の進化
 言語聴覚士は、「話す」「聞く」「食べる」といった機能に困難を抱える方を支援する国家資格の専門職です。一方、認定言語聴覚士は、その中でも特定の専門領域において、より深い知識と実践的なスキルを備えた上位資格者です。
言語聴覚士は、「話す」「聞く」「食べる」といった機能に困難を抱える方を支援する国家資格の専門職です。一方、認定言語聴覚士は、その中でも特定の専門領域において、より深い知識と実践的なスキルを備えた上位資格者です。
つまり、認定言語聴覚士は、STとしての基礎能力を土台に、「高度な業務を安全かつ専門的に遂行できるレベル」を認められた人材といえます。
認定言語聴覚士になるには
どれくらいの経験年数が必要か?
 認定言語聴覚士は、資格取得後すぐに目指せるものではありません。
認定言語聴覚士は、資格取得後すぐに目指せるものではありません。
ある程度の臨床経験と、専門領域での継続的な実務が求められる中堅〜ベテラン向けのステップアップ資格です。
認定言語聴覚士の申請に必要な経験年数と条件をわかりやすく整理します。
原則として5年以上の臨床経験が必要
まず最も基本的な条件として、言語聴覚士としての実務経験が5年以上あることが求められます。
この年数は「なんとなく働いていた期間」ではなく、対象者としっかり向き合い、専門職としての判断や対応を重ねてきた期間であることが重要です。
5年という期間は短いようで長く、申請時にはその中で得た学びや実績が問われることになります。
日々の臨床記録や症例のメモを残しておくことで、後の症例報告書の作成にも役立ちます。
申請時点で3年以上同一分野での実務経験が必要
もうひとつのポイントは、申請を希望する分野において、3年以上の継続的な実務経験があることです。
たとえば「摂食嚥下障害」領域で認定を受けたい場合、その領域で3年以上の支援実績や担当症例が必要になります。
この条件は、特定の分野に特化した経験があるかどうかを確認するためのもの。
広く浅くではなく、ひとつの領域を深く掘り下げてきた経験が認定の前提となります。
協会会員としての継続年数も条件に含まれる
加えて、日本言語聴覚士協会の正会員であり、かつ継続的に在籍していることも申請条件の一つです。
途中で退会・再入会を繰り返していると、その年数が条件を満たさない場合があるため注意が必要です。
また、協会会員であることにより、研修の受講や最新情報へのアクセスが可能になるという実務上のメリットもあります。
認定取得を視野に入れている方は、早い段階で会員登録を済ませておくことをおすすめします。
認定言語聴覚士になるための
研修制度
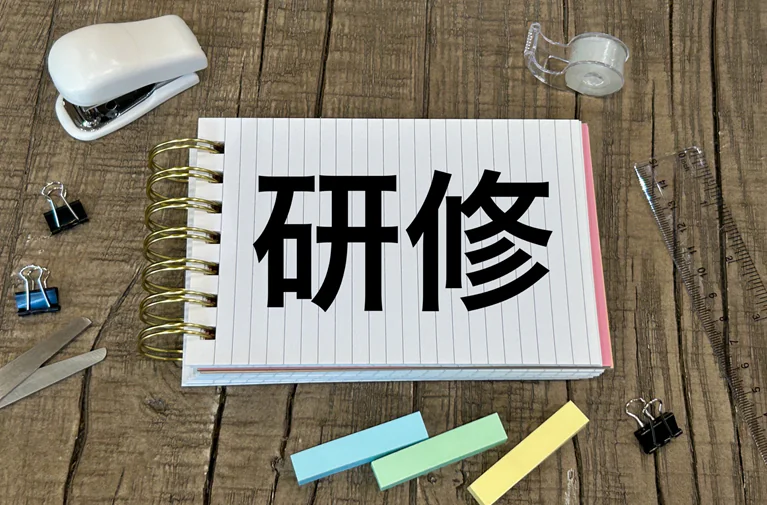 認定言語聴覚士になるには、実務経験だけでなく、日本言語聴覚士協会が定める「専門研修」の修了が必須条件となっています。
認定言語聴覚士になるには、実務経験だけでなく、日本言語聴覚士協会が定める「専門研修」の修了が必須条件となっています。
この研修制度は、専門性を高めるために体系的に設計されており、対象分野に応じて内容も異なります。
ここでは、研修の形式や内容、分野ごとのプログラムの特徴について解説します。
日本言語聴覚士協会主催の専門研修を受講する必要がある
認定言語聴覚士の研修は、日本言語聴覚士協会(ST協会)が主催する指定の研修を受講し、修了することが前提となります。
これらの研修は各分野のエキスパートによって構成されており、臨床現場での応用を意識した実践的な内容が中心です。
講義、グループワーク、症例検討、文献の読み解きなど、単なる座学にとどまらず、多角的なアプローチで学びを深めるプログラムになっています。
Eラーニングや集合研修など多様な形式で行われている
近年では、受講しやすさを考慮して、eラーニング形式での研修も導入されています。
これにより、地方在住や多忙な勤務状況にあるSTでも、スケジュールに合わせて学べる柔軟性が高まりました。
ただし、すべてがオンラインで完結するわけではなく、分野によっては集合研修や演習への参加が必須となることもあります。
年度ごとに開催内容が更新されるため、希望分野の最新情報をチェックして早めに準備することが大切です。
分野ごとの研修プログラムが用意されている
研修は、認定を希望する分野ごとに内容が異なります。たとえば、失語・高次脳機能障害領域では、評価法や代償手段、環境調整の支援方法を中心に学びます。
摂食嚥下障害領域では、嚥下機能評価(VF・VE)や栄養・食形態の知識などを深掘りします。
小児コミュニケーション障害領域では、発達段階に応じたアプローチ、保護者支援、環境構築などがテーマです。
このように、分野に応じた実践的な内容が用意されており、「現場ですぐ活かせる力」を高めることができるのが、認定研修の大きな特長です。
認定言語聴覚士になるための
手続き
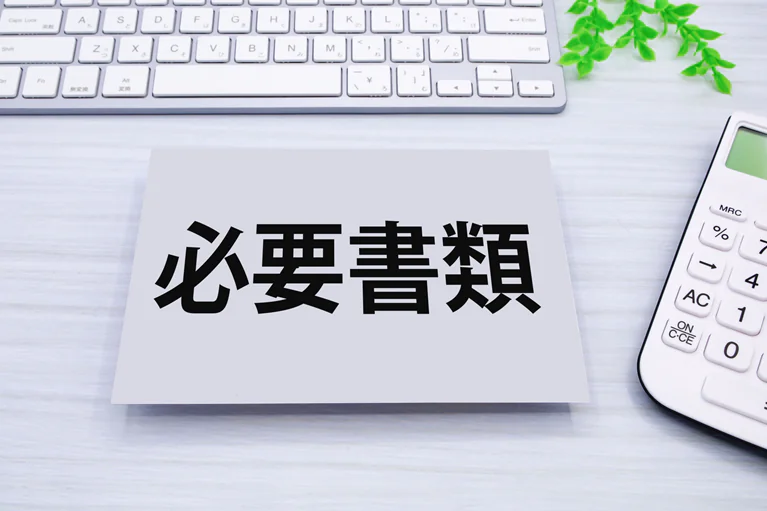 認定言語聴覚士になるためには、臨床経験や研修の修了だけでなく、所定の手続きと書類提出が必要です。
認定言語聴覚士になるためには、臨床経験や研修の修了だけでなく、所定の手続きと書類提出が必要です。
これらは資格としての信頼性を確保するための大切なステップであり、丁寧に準備することで審査の通過率も高まります。
ここでは、取得までの流れと各手続きのポイントについて解説します。
研修修了後に症例報告書を提出する必要
認定申請の中でも特に重要なのが、症例報告書の提出です。
これは、これまで実際に支援した対象者について、評価・方針・介入・結果・考察といった流れを論理的かつ実践的にまとめたものです。
報告書は、研修で学んだ知識や技術をもとに、どのように実際の現場で活かしているかを示す資料でもあります。形式や分量は分野によって異なりますが、いずれも対象者への深い理解と専門的な支援を行った実績が問われる内容となっています。
協会への申請書類の提出と審査が行われる
症例報告書とあわせて、以下のような各種申請書類の提出が求められます。
- 認定申請書
- 実務経験証明書(勤務先からの発行)
- 協会会員であることの証明
- 研修修了証の写し など
これらの書類をそろえて提出後、協会による審査(書類審査・必要に応じて面接)が行われます。
審査には一定の期間を要し、認定の可否は書面にて通知されるのが一般的です。
認定後も定期的な更新申請が必要
認定言語聴覚士は一度取得すれば永久に有効というわけではなく、一定期間ごとに更新が必要な資格です。
多くの場合、有効期限は5年間とされており、その間に継続教育や学会発表、臨床実績などの要件を満たさなければなりません。
更新の際には再度、活動実績の報告や教育研修への参加証明の提出が求められるため、日頃からの記録と振り返りが重要です。
“取りっぱなし”ではなく、“学び続ける専門職”としての姿勢が求められる制度です。
認定言語聴覚士になることで
得られるメリット
 認定言語聴覚士の取得には、一定の時間や労力が必要ですが、それに見合うだけの実践的な価値とメリットがあります。
認定言語聴覚士の取得には、一定の時間や労力が必要ですが、それに見合うだけの実践的な価値とメリットがあります。
この資格を通じて得られるのは「肩書き」だけではなく、臨床現場やキャリアにおける信頼と可能性の広がりです。
ここでは、認定資格を取得することの主なメリットを具体的に紹介します。
専門性を客観的に証明できる
認定言語聴覚士は、日本言語聴覚士協会によって一定の基準を満たした専門性があると認められた証です。
つまり、自分の経験や技術を「資格」という形で客観的に示すことができ、第三者からの信頼を得やすくなるのが大きなポイントです。
特に転職や異動、新しいプロジェクトへの参加などにおいて、「この人はその分野の専門家」として評価されやすくなります。
職場での信頼や評価が高まる
現場では、言語聴覚士の力量が数字で測れるものではないぶん、認定資格を持っているかどうかが判断材料になることもあります。
認定STになることで、職場内での評価が高まり、
- 難しい症例の担当を任される
- カンファレンスで発言が求められる
- 他職種からの相談が増える
といったように、自然と“中心人物”としての役割を担う機会が増えていくことがあります。
研究会や講師などの活動機会が増える
認定を受けると、専門分野での発表・研究・教育などの活動機会が広がるのもメリットです。
地域の勉強会や協会主催のセミナーで講師を務めたり、実習生の指導担当になったりと、“伝える立場”としての経験が増えていきます。
また、自分の考えや臨床スタイルをアウトプットする場に恵まれることで、より深い学びや自己成長にもつながります。
キャリアアップや転職時のアピールになる
認定資格は、昇進や異動希望、転職の際の強力なアピールポイントにもなります。
実際、求人票に「認定言語聴覚士優遇」などの文言が記載されているケースもあり、キャリア形成において有利に働くことは間違いありません。
また、将来的に専門職リーダーや管理職を目指す際にも、「認定を持っていること」が推薦や選抜の基準となる職場も増えています。
高度な臨床スキルによる質の高い支援が可能
認定言語聴覚士として求められるのは、単なる知識の量ではなく、現場で“応用できる力”です。
資格取得の過程では、臨床例に基づいた深い学びやケーススタディが求められるため、自然と実践的で柔軟な対応力が磨かれます。
その結果、難しい症例に対しても、より的確な評価と訓練プランを立てることができ、対象者の回復や生活の質(QOL)向上に直結する支援が可能になります。
指導者としての活躍と社会的貢献ができる
認定言語聴覚士は、後進の育成や地域支援の中心的役割を担う存在としても期待されます。
新人STへのOJT指導、施設内勉強会の開催、学会や研修会での講師など、教育者・指導者として活躍の場が広がります。
また、地域連携の中では、複数の事業所や施設をつなぐコーディネーターとしての立場で、支援体制づくりに貢献するケースも増えています。
このように、認定資格は“個人のスキル向上”を超えて、社会的な役割を広げる力も持っています。
認定言語聴覚士の分野別の
認定内容とは?
認定言語聴覚士の資格は、特定の専門領域において深い知識と実践力を備えていることを証明する制度です。
申請時には、自分が認定を希望する分野を選ぶ必要があり、それぞれの分野に対応した研修や症例報告が求められます。
ここでは、代表的な5つの分野について簡潔に解説します。
失語・高次脳機能障害領域
この分野では、脳卒中や外傷などによって生じた言語理解・発話の障害、高次脳機能の低下に対する支援に特化します。
言語訓練だけでなく、注意・記憶・遂行機能などの認知的側面への介入も含まれ、
多職種と連携しながら生活機能の改善を目指す包括的な支援が求められます。
摂食嚥下障害領域
この領域は、安全な食事動作の確保と誤嚥予防に関わる専門性が求められます。
VF(嚥下造影)やVE(嚥下内視鏡)などの検査への対応力はもちろん、食形態、姿勢、栄養管理に関する知識も必要です。
病院や老健施設、訪問リハビリなどでの需要が高く、臨床でもっとも取得者が多い分野のひとつです。
発声発語・構音障害領域
声や発音に関する問題に焦点を当てるこの分野では、声帯障害・構音異常・音声訓練などへの専門的対応が求められます。
小児〜成人まで幅広い対象者が含まれ、発声訓練や呼吸訓練、補助発話手段の選定といった技術も含まれます。
とくに、医師や耳鼻咽喉科との連携の中で活躍する機会が多い領域です。
小児コミュニケーション障害領域
発達障害や言語発達の遅れを持つ子どもたちへの支援が中心の分野です。
発語の促進、語彙の獲得、発達段階に応じた言語訓練を行い、
子ども本人だけでなく、保護者や教育機関と連携して支援環境を整える視点も重視されます。
保育園、特別支援学校、療育施設など、小児分野で働くSTに人気のある認定領域です。
認知症領域などの分野別認定がある
そのほか、認知症領域という高齢化社会における重要な分野も認定対象に含まれています。
この分野では、認知症の進行によるコミュニケーション障害や食事の困難さに対し、本人と家族の両方を支援する視点が求められます。
近年は「地域包括ケア」の観点から、認知症領域の認定資格を持つ言語聴覚士のニーズも高まってきています。
認定言語聴覚士になるための
よくある質問
特に寄せられることの多い4つの質問に対して、制度の実情を踏まえてわかりやすくお答えします。
認定言語聴覚士は、誰でも受験できますか?
いいえ。まずは言語聴覚士の国家資格を取得し、原則として5年以上の臨床経験が必要です。さらに、日本言語聴覚士協会が定める専門プログラムや講習会への参加、学会等の研修ポイント取得なども要件に含まれています。
認定言語聴覚士は国家資格ですか?
いいえ。認定言語聴覚士は日本言語聴覚士協会が認定する民間資格です。ただし、一定の基準に基づいた厳格な審査を経て認定されるため、専門性を証明する資格として現場での信頼性は非常に高いとされています。
どの専門領域を選べばいいかわかりません。どうやって決めるべきですか?
自分の臨床経験や関心、将来のキャリアプランをもとに選ぶのが基本です。たとえば、嚥下に強い関心があれば摂食嚥下障害領域、子どもの言語発達に携わりたいなら言語発達障害領域など、日々の実践を通じて関心のある分野を見つけていくことが重要です。
認定言語聴覚士の資格を取得することで、どんなメリットがありますか?
主に以下のようなメリットがあります。
- 専門性の証明による職場での信頼性向上
- キャリアアップ(昇進・転職・手当など)
- 難症例対応の自信と実力の向上
- 教育・地域連携でのリーダー的役割の獲得
認定言語聴覚士の資格の有効期限はありますか?
はい、認定言語聴覚士の資格には有効期限があり、原則として5年ごとの更新制となっています。
認定後も「学び続ける姿勢」が求められ、更新時には活動実績の報告や、継続教育の受講などの条件を満たす必要があります。
この更新制度によって、資格の信頼性と専門性が継続的に担保される仕組みになっています。
認定言語聴覚士の更新にはどんな実績が必要ですか?
更新時に求められる実績は以下のようなものが代表的です:
- 臨床現場での継続的な活動
- 関連分野での研修受講や学会参加
- 症例報告や発表、論文執筆など(あれば)
- 地域活動や後進育成への関与など
これらをまとめた業績報告書の提出が基本となります。
あらかじめ実績を意識して積み重ね、年度ごとに記録を残しておくと、更新時に慌てず対応できます。
認定言語聴覚士の症例報告はどのくらいの分量ですか?
症例報告の分量は、認定を申請する分野や協会のガイドラインによって異なりますが、
おおむねA4用紙で5〜10枚程度が目安とされています。
内容としては、
- 対象者の背景・評価結果
- 支援方針と根拠
- 実施した訓練内容とその結果
- 今後の課題と自己評価
といった流れを論理的に、かつ臨床に即して記述する必要があります。
表面的な記録だけでなく、「なぜこの支援を選んだのか」「その結果どうだったか」を明確に書けることがポイントです。
複数の認定分野を同時に取得できますか?
はい、認定言語聴覚士の制度では、複数の分野を取得することが可能です。
ただし、分野ごとに研修修了や症例報告の提出が必要となるため、同時取得には相応の準備期間と実務経験が求められます。
たとえば「摂食嚥下領域」と「認知症領域」を両方取得したい場合、それぞれの要件(3年以上の実務経験、研修、報告書など)を個別に満たす必要があります。
一度に2分野以上を目指す場合は、計画的にスケジュールを立てることが成功の鍵になります。
まとめ:認定言語聴覚士を目指す価値と今後の展望
言語聴覚士として臨床経験を積んでいく中で、「より高度な支援を提供したい」「専門性を深めたい」と感じるタイミングは誰にでも訪れるものです。そんなときに、認定言語聴覚士という資格は、自分自身の能力をさらに高め、次のステージへ進むための明確な道しるべとなってくれます。
認定言語聴覚士は、特定の専門領域における高度な知識と実践力を証明する資格であり、臨床の質を上げるだけでなく、職場での評価やキャリアアップ、後進指導や地域貢献といった広がりある働き方を可能にします。
また、資格取得のプロセスそのものが、日々の臨床を振り返り、学びを深める貴重な成長の機会にもなります。
さらに今後は、高齢化の進展や医療の高度化に伴い、「質の高い支援ができるST」がますます求められる時代に入っていきます。言語聴覚士として社会に信頼され、より多くの人の暮らしを支える存在になるためには、認定資格の取得は非常に大きな武器となるでしょう。
自分の専門性を高めたい、信頼される存在になりたい、未来のSTを育てたい——そんな思いを持つあなたにとって、認定言語聴覚士はきっと目指す価値のある資格です。
努力の先には、これまで以上に広いフィールドとやりがいが待っています。
言語聴覚士におすすめの
転職サイトランキング
トップ3「ミチビーク調べ」
参考記事:言語聴覚士(ST)におすすめの転職サイト・エージェント10選をランキング形式で一挙紹介!の記事はこちら
この記事の運営者情報
| メディア名 | ミチビーク |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社Method innovation |
| 会社ホームページ | https://www.method-innovation.co.jp/ |
| 所在地 |
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町3丁目6番11号 BADGE長堀BLD. 2階
|
| 代表取締役 | 清水 太一 |
| 設立 | 2016年11月1日 |
| 事業内容 | 集患支援事業 メディア運営事業 広告代理店事業 |
| お問い合わせ | michibi-Qのお問い合わせはこちら |