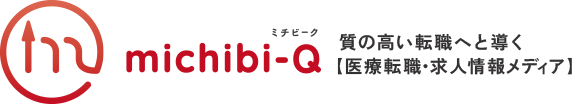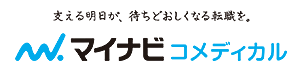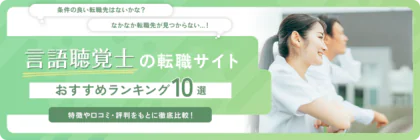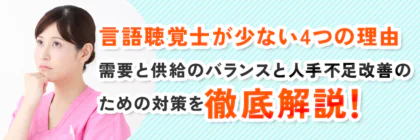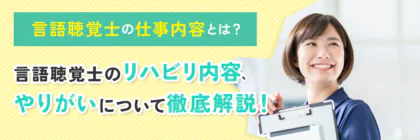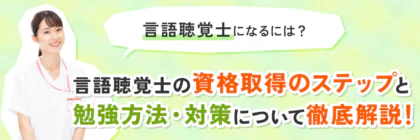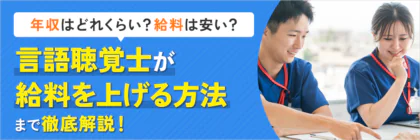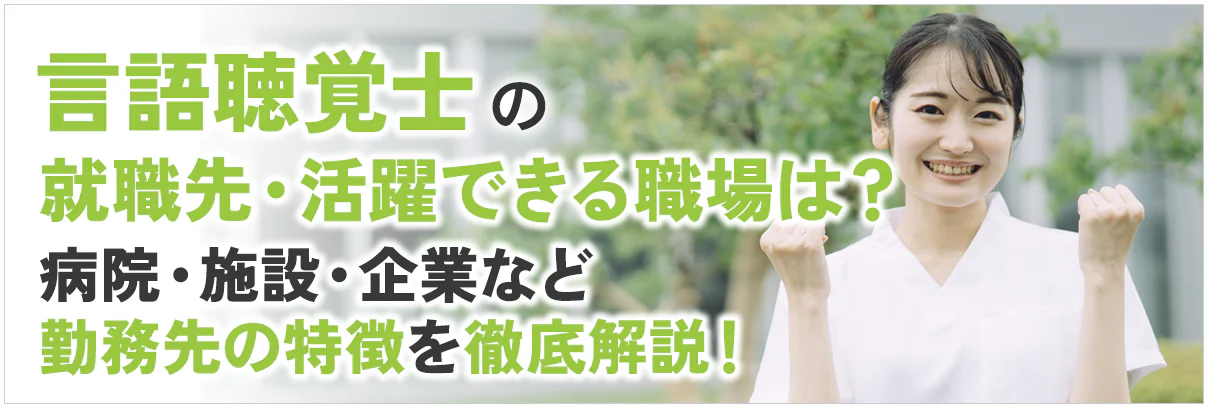
※当サイト(ミチビーク)はアフィリエイト広告を掲載しています。
言語聴覚士におすすめの
転職サイトランキング
トップ3「ミチビーク調べ」
さらに参考記事:言語聴覚士(ST)におすすめの転職サイト・エージェント10選をランキング形式で一挙紹介!の記事もぜひご覧ください!
国家資格として幅広いフィールドで活躍できる一方で、「具体的にどんな就職先があるの?」「病院以外でも働けるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実は、言語聴覚士の活躍の場は年々広がっており、医療機関だけでなく、教育現場、福祉施設、一般企業などにもニーズが高まっています。
この記事では、言語聴覚士の主な就職先を一覧形式で紹介し、それぞれの特徴や役割をわかりやすく解説します。
これから就職・転職を考えている方や、キャリアの選択肢を広げたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
言語聴覚士の就職先一覧を
わかりやすく紹介
言語聴覚士の働き方は、医療・介護・教育・民間企業など多岐にわたります。
ここでは、主な勤務先を一覧で整理し、それぞれの概要や特徴を簡単にご紹介します。
医療機関
 言語聴覚士の就職先として最も多いのが、病院やクリニックなどの医療機関です。厚生労働省の調査でも、STのおよそ7割が医療機関に勤務しているとされています。
言語聴覚士の就職先として最も多いのが、病院やクリニックなどの医療機関です。厚生労働省の調査でも、STのおよそ7割が医療機関に勤務しているとされています。
特に、脳卒中後の失語症や嚥下障害、高次脳機能障害といった疾患に対応するリハビリテーションの場面では、STの専門性が強く求められます。
総合病院・リハビリ専門病院・各種クリニックでの役割を紹介し、多職種連携の中でどのように言語聴覚士が活躍しているのかを具体的に解説します。
総合病院・リハビリ専門病院
総合病院やリハビリテーション病院では、STは医師、看護師、理学療法士、作業療法士などの他職種と連携し、患者の言語・コミュニケーション・嚥下機能の回復を目指す専門職として配置されます。
特に、脳卒中や頭部外傷、神経難病(パーキンソン病など)、がん治療(口腔がん・喉頭がん)の術後に起こる言語障害や嚥下障害などに対して、STは早期から評価と訓練を行い、退院後の生活を見据えた支援を行います。
病期としては、「急性期」「回復期」「生活期」のすべてで関わることが多く、幅広い知識と臨床スキルが求められる現場です。
急性期病院は医療処置が多く高い専門性が求められる
急性期病院とは、手術や発症直後の治療を行う医療機関です。
ここでの言語聴覚士の役割は、早期のリスク評価や迅速な嚥下機能評価が中心となります。
脳卒中や外傷後の患者に対し、嚥下造影検査(VF)や嚥下内視鏡検査(VE)の補助を行い、安全な食事再開をサポートします。
また、急性期では患者の状態が刻々と変化するため、医師や看護師との密な連携が必要不可欠。
医学的知識と迅速な判断力が求められる場面が多く、スキルアップのスピードも早い環境です。
回復期病院では在宅復帰に向けた集中的なリハビリを行う
回復期病院では、主に在宅復帰を目指すリハビリテーションが中心です。
脳血管疾患や整形外科手術の後に入院し、1日2〜3単位の集中的なリハビリが行われます。
言語聴覚士は、失語症・構音障害・高次脳機能障害・摂食嚥下障害などに対するリハビリを担当。
評価から訓練、家族指導や自宅環境へのアドバイスまで幅広く関わります。
このフェーズでは、患者とじっくり向き合える時間があるため、生活全体を見据えた支援ができるのが大きな魅力です。
慢性期病院は長期的なケアと信頼関係の構築が重視される
慢性期病院では、医療処置が終わった後も継続的なケアが必要な方が多く入院しています。
このような環境では、言語聴覚士の支援も中長期的な視点で行われるのが特徴です。
嚥下機能の維持・悪化予防や、認知機能の低下に伴うコミュニケーション支援が主な業務内容となります。
一人の患者さんと長く関わるため、信頼関係を深めながら、生活の質(QOL)を支えるリハビリが求められます。
クリニック(耳鼻咽喉科・歯科・小児科など)
耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、小児科、脳神経外科、形成外科などのクリニックでも、STのニーズは高まっています。
これらのクリニックでは、以下のような専門的な疾患・障害に特化した支援を行うことが一般的です。
| クリニックの診療科 | 主な対象とする障害 | STの主な業務 |
|---|---|---|
| 耳鼻咽喉科 | 聴覚障害、音声障害 | 聴力検査、補聴器リハ、音声訓練 |
| 歯科口腔外科 | 摂食・嚥下障害、構音障害 | 嚥下評価、咀嚼訓練、食形態指導 |
| 小児科 | 発達性言語障害、構音障害 | 発音訓練、遊戯療法、保護者指導 |
| 脳神経外科 | 高次脳機能障害、嚥下障害、構音障害 | 嚥下評価、言語訓練、認知リハビリ |
| 形成外科(口蓋裂など) | 口蓋裂、発音異常 | 口腔機能訓練、構音矯正 |
こうしたクリニックは、特定のニーズに特化した専門職としてSTの力が発揮される場所でもあります。
介護・福祉分野
 高齢化が進む日本において、介護・福祉の分野で言語聴覚士(ST)のニーズはますます高まっています。 特に、加齢に伴う嚥下障害や認知症に起因するコミュニケーション障害などへの対応が求められ、STはQOL(生活の質)を維持・向上させる役割を担っています。
高齢化が進む日本において、介護・福祉の分野で言語聴覚士(ST)のニーズはますます高まっています。 特に、加齢に伴う嚥下障害や認知症に起因するコミュニケーション障害などへの対応が求められ、STはQOL(生活の質)を維持・向上させる役割を担っています。
また、障害者福祉や児童発達支援の分野でも、発達障害や言語発達遅滞を持つ子どもたちの支援が重要な役割となっており、STは医療機関以外でも幅広く活躍できる職種として注目されています。
高齢者福祉施設、通所系サービス、在宅支援、障害福祉施設など、さまざまな福祉現場における言語聴覚士の業務内容と特性を具体的に紹介します。
介護老人保健施設や特別養護老人ホーム
高齢化が進む日本において、介護・福祉の分野で言語聴覚士(ST)のニーズはますます高まっています。 特に、加齢に伴う嚥下障害や認知症に起因するコミュニケーション障害などへの対応が求められ、STはQOL(生活の質)を維持・向上させる役割を担っています。
また、障害者福祉や児童発達支援の分野でも、発達障害や言語発達遅滞を持つ子どもたちの支援が重要な役割となっており、STは医療機関以外でも幅広く活躍できる職種として注目されています。
| 施設種別 | 主な対象者 | STの主な業務 |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 退院後、在宅復帰を目指す高齢者 | 嚥下評価・訓練、退所後支援、口腔体操 |
| 特別養護老人 | 在宅復帰が難しい要介護高齢者 | 嚥下機能の維持、口腔ケア指導、介護スタッフとの連携 |
これらの施設では、食事支援や集団訓練の企画なども行い、STがチームの中核として働くケースも多いです。
デイサービス・訪問リハビリテーション
デイサービスや訪問リハビリテーションは、通所・在宅の生活期支援の場です。ここでは、通所利用者や在宅療養者ができるだけ自立して生活を続けられるようサポートします。
訪問では、実際の生活環境に合わせた支援ができるため、より実践的・生活密着型の介入が可能です。
| サービス種別 | 特徴 | STの業務例 |
|---|---|---|
| デイサービス・デイケア | 日中のみ利用 | 嚥下訓練、口腔体操、集団コミュニケーション |
| 訪問リハ | 自宅で実施 | 食形態の調整、介助者への指導、在宅嚥下支援 |
介護老人保健施設では嚥下訓練やコミュニケーション支援が中心
介護老人保健施設(老健)は、在宅復帰を目指す高齢者が一時的に入所する中間的な施設です。
この環境での言語聴覚士の主な役割は、嚥下機能の評価・訓練、食事形態の調整、失語症や構音障害への対応などが中心となります。
また、食事中の観察や多職種会議での発言、家族へのアドバイスも業務の一部です。
「食べる力」と「話す力」を支えることで、利用者の生活の質(QOL)を高める支援が求められます。
デイケアでは生活リハビリと家族支援が求められる
デイケア(通所リハビリ)では、利用者が日帰りで施設に通いながら機能回復を目指すサービスが提供されます。
言語聴覚士は、コミュニケーション訓練や嚥下体操、発声練習、認知機能への働きかけなどを行い、「生活に直結したリハビリ」を担当します。
さらに、利用者の変化に気づき、家族やケアマネジャーに情報を共有する役割もあり、現場との連携が非常に重要になります。
訪問リハでは自宅での生活に合わせた個別対応ができる
訪問リハビリは、利用者の自宅に直接訪問してリハビリを行うサービスです。
この働き方では、家庭の環境、生活スタイル、家族構成に合わせた支援をオーダーメイドで提供できるのが大きな魅力です。
たとえば、嚥下障害がある方に対しては、実際の食事場面を見ながら、座る位置・食具・食事内容の調整を提案するなど、現場でしかできない支援が可能です。
また、利用者と1対1で深く関わることができるため、信頼関係の構築や生活全体を見渡す視点が養われる現場でもあります。
障害者支援施設・児童発達支援センター
福祉の分野では、障害をもつ子どもや成人への支援も重要な分野です。言語発達の遅れや発達障害、構音障害などに対し、専門的な訓練と家族支援を行います。
特に、児童発達支援センターや放課後等デイサービスでは、遊びを通じた言語訓練や集団適応支援が重視され、保育士や作業療法士との連携が求められます。
| 支援施設 | 主な対象 | STの業務例 |
|---|---|---|
| デイサービス・デイケア | 成人(知的・身体・発達障害) | 発語訓練、生活スキル支援、就労支援 |
| 児童発達支援センター | 未就学児 | 言語発達支援、遊びを通じた訓練 |
| 放課後等デイサービス | 小中高生 | コミュニケーション訓練、学習支援 |
発達支援分野では、子ども一人ひとりの個性を尊重しながら関わる姿勢が何より重要です。
教育・研究機関
言語聴覚士の活躍の場は医療や福祉にとどまらず、教育・研究の現場にも広がっています。 特に、特別支援教育の分野や、言語聴覚士養成校・大学での教育職、研究職としての役割は、今後の人材育成や学問的発展において欠かせない存在です。
子どもへの支援を行う学校現場と、教育・研究を担う養成機関の2つの分野に分けて、言語聴覚士の働き方と役割を詳しく解説します。
特別支援学校・学級における支援
特別支援学校や、一般校の特別支援学級では、発達障害や聴覚障害、構音障害などを持つ児童生徒に対し、学習と生活への適応を支援することがSTの主な役割です。
教育現場におけるSTは、教員や養護教諭と連携しながら、個別の支援計画に基づいた支援を行い、本人の発達段階に応じた指導を行います。
また、保護者や教職員へのアドバイスを通じて、家庭や学校生活全体の質を高めるサポートも行います。
| 学校種別 | 主な対象 | STの業務例 |
|---|---|---|
| 特別支援学校 | 成人(知的・身体・発達障害) | 言語訓練、学習支援、教員への指導助言 |
| 特別支援学級(小中高) | 発達障害・言語障害を持つ児童生徒 | 個別対応、集団適応支援、保護者面談 |
学校現場では、教育の視点と医療的支援の橋渡し役として、STの存在が非常に重要視されています。
養成校や大学での教員・研究者の役割
言語聴覚士の資格を取得するには、厚生労働省認定の養成校や大学での教育課程を修了する必要があります。そこで教鞭をとる教員の中には、現場経験を積んだSTがキャリアチェンジをして教育職に就くケースも多く見られます。
また、大学の研究機関などでは、言語聴覚療法の有効性や新しいリハビリ手法に関する研究を行う研究者として、STが活躍することもあります。
| 学校種別 | 主な対象 | STの業務例 |
|---|---|---|
| 特別支援学校 | 成人(知的・身体・発達障害) | 言語訓練、学習支援、教員への指導助言 |
| 特別支援学級(小中高) | 発達障害・言語障害を持つ児童生徒 | 個別対応、集 |
この分野では、高度な専門知識と論理的思考、後進育成への情熱が求められます。
企業・行政・独立などその他の就職先
言語聴覚士の就職先は、医療や福祉、教育にとどまらず、企業や行政機関、さらには独立開業といった多様な選択肢にも広がっています。専門職としての知識とスキルは、製品開発や地域福祉、保健予防活動など、多方面で活かすことが可能です。
あまり知られていないけれども重要な活躍の場である「行政・企業・独立」の分野に焦点を当て、それぞれでの業務内容や特徴、向いている人の傾向について紹介します。
保健所や市町村などの公的機関
地域の保健センターや市町村の福祉課などで、住民の健康増進や介護予防の取り組みに関わるSTもいます。特に、乳幼児健診での言語・発達の相談や、高齢者の嚥下機能スクリーニングなどが中心的な業務です。
行政機関で働くSTは、個別支援というよりも「地域単位での健康づくり」や「早期発見・予防」を目的とした活動が多くなります。多職種と連携し、地域包括ケアシステムの一員として働く点が特徴です。
| 公的機関 | 主な対象 | STの業務例 |
|---|---|---|
| 保健所・保健センター | 乳幼児、高齢者、障害者 | 発達相談、嚥下スクリーニング、健康教室講師 |
地域との関わりが好きな人、予防医療や社会貢献に関心のある人に向いています。
補聴器メーカー・医療機器メーカー等の企業就職
STは、「聞く」「話す」「飲み込む」という機能に関する深い専門知識を持っているため、補聴器メーカーや嚥下関連の医療機器を扱う企業でも高いニーズがあります。
企業での仕事は、以下のように多岐にわたります。
- 製品開発に関わるアドバイザー
- 顧客対応(説明・フィッティングなど)
- 医療機関や販売代理店への営業・研修サポート
- 市場調査や技術検証
| 企業種別 | STの活躍の例 |
|---|---|
| 補聴器メーカー | 聴力測定、適合支援、技術営業 |
| 嚥下食・機器開発企業 | 商品開発アドバイザー、セミナー講師 |
| 医療機器販売 | 顧客向け製品説明、医療関係者への研修支援 |
現場の経験を活かして“ものづくり”や“販売支援”の分野で活躍したい方におすすめです。
フリーランスや起業で活動の幅が広がっている
 近年は、フリーランスとして活動する言語聴覚士も少しずつ増えてきています。
近年は、フリーランスとして活動する言語聴覚士も少しずつ増えてきています。
たとえば、自分でオンライン言語訓練サービスを立ち上げたり、訪問専門のリハビリサービスを提供したり、個人事業として講演や研修を請け負う人もいます。
こうした働き方は自由度が高い分、営業・広報・企画など、ビジネススキルも必要となります。
ですが、臨床以外の強みを活かして、「自分らしい働き方をつくる」という点では、今後さらに注目されるスタイルです。
言語聴覚士の就職先選びで
押さえておきたいポイントとは?
 言語聴覚士の就職先は多岐にわたるため、選択肢が広い分、「自分に合った職場がわからない」と迷う方も少なくありません。
言語聴覚士の就職先は多岐にわたるため、選択肢が広い分、「自分に合った職場がわからない」と迷う方も少なくありません。
せっかく専門性の高い資格を持っていても、環境が合わなければ本来の力を発揮しにくくなってしまいます。
ここでは、言語聴覚士が就職先を選ぶ際に押さえておきたい重要な視点を紹介します。
対象とする年齢層(小児〜高齢者)を明確にする
言語聴覚士は小児から高齢者まで幅広い年代の対象者と関わる職業です。
そのため、自分が「どの年齢層に強みを持ちたいか」「どの世代に関わりたいか」を明確にしておくと、職場選びの軸がぶれにくくなります。
たとえば、小児領域で発語や発達を支援したいなら保育園・療育施設へ、嚥下障害のリハビリに関心があるなら病院や老健施設へ、といった具合に、対象層に合った職場選びが重要です。
ライフスタイルに合った働き方ができるか確認する
勤務時間や休日、シフトの柔軟さなど、ライフスタイルに合った働き方ができるかどうかも大切なポイントです。
たとえば、子育てや介護をしながら働きたい方には、時短勤務やパート制度のある職場が向いています。
訪問リハやフリーランスなどは、比較的自由なスケジュールで働ける反面、自己管理が必要です。
どれだけやりがいがあっても、長く続けられる環境でなければキャリアが途切れてしまう可能性があります。
働き方・待遇・教育体制をチェックする
就職先を選ぶ際には、業務内容だけでなく、働く環境そのものにも目を向けることが重要です。具体的には以下のような点をチェックしましょう。
- 勤務形態:常勤・非常勤、シフト制か日勤のみか
- 福利厚生:休日数、残業の有無、産休・育休の取得実績
- 教育体制:新人研修の有無、OJT(現場指導)の充実度
- 職場の雰囲気:見学やインターンシップで確認可能
また、現場で働く言語聴覚士の声を聞くのも有効です。できれば事前に見学や説明会に参加し、自分の目で職場の雰囲気を確かめることをおすすめします。
チーム医療や連携体制が整っているか確認する
言語聴覚士は、医師・看護師・介護職・作業療法士・理学療法士などとの連携が欠かせない仕事です。
そのため、職場選びでは「チーム医療が機能しているか」「他職種との連携体制がしっかりしているか」を確認することも重要です。
連携体制が不十分な職場では、STとしての専門性が発揮しづらく、孤立感を感じることもあります。
風通しのよい職場環境かどうかを見極めることが、働きやすさに直結します。
キャリアアップ・資格取得支援の有無も重要
将来的に専門性を深めていきたいと考える方にとっては、就職先がキャリア支援に積極的かどうかもチェックポイントになります。
たとえば、
- 認定言語聴覚士の取得支援制度(学会費の補助、研修費支援など)
- 学会・研修への参加に対する出張扱いや勤務調整の有無
- 上位資格保有者(指導者)の在籍数とフォロー体制
これらの制度が整っている職場は、スキルアップのモチベーションを保ちやすく、長期的な成長につながりやすいです。
言語聴覚士の就職先に関する
よくある質問
言語聴覚士として働くうえで、「病院以外にも活躍の場はあるの?」「小児に関わるにはどうすればいい?」など、
就職先に関する疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。
ここでは、特に多く寄せられる4つの質問に対して、現場の実情をふまえてわかりやすく回答していきます。
言語聴覚士の就職先で一番多いのはどこですか?
最も多いのは病院などの医療機関です。特に総合病院やリハビリテーション専門病院では、脳卒中後のリハビリや嚥下訓練などを中心に活躍の場が多く、言語聴覚士全体の約7割が医療系に就職しています。
福祉施設で働く言語聴覚士の仕事はどんなことをしますか?
高齢者施設や障害者福祉施設では、嚥下機能の訓練やコミュニケーション支援を中心に、日常生活の質を高めるためのリハビリを行います。チームでの連携や介護職との協力も大切な業務のひとつです。
学校で言語聴覚士として働くにはどうしたらいいですか?
特別支援学校や特別支援学級に配置されるSTとして働く場合、自治体や教育委員会の採用枠に応募するか、学校と直接契約を結ぶケースが多いです。教育現場での経験があると有利ですが、臨床経験を活かして採用されるケースも増えています。
企業や行政機関でのSTの就職は珍しいですか?
数としては多くありませんが、補聴器メーカーや保健センターなどで専門性を活かして働くSTは増えています。 特に、発達相談や地域支援、製品開発や営業サポートといった分野で活躍できます。ニッチですが将来性のある働き方です。
病院以外で働く言語聴覚士は多いのでしょうか?
はい、近年では病院以外で活躍する言語聴覚士も増えています。
介護施設、訪問リハビリ、療育施設、教育機関、さらには企業や自治体の職員として働くケースもあります。
特に高齢化や発達障害への理解が進む中で、医療以外の分野でもSTの専門性が必要とされる場面が増えているのが現状です。
勤務先の幅が広がっている今、自分のライフスタイルや関心に合った分野を選びやすくなっています。
小児分野に強い職場はどこですか?
小児領域に強い職場としては、以下のような就職先が挙げられます。
- 保育園(発達支援を導入している園)
- 特別支援学校
- 児童発達支援センター
- 療育施設(発達障害支援が中心)
- 放課後等デイサービス(発達支援企業が運営)
これらの職場では、発語・言語理解・発達支援などを専門的にサポートする役割が求められます。
小児領域を希望する場合は、「対象年齢」「支援内容」「保護者支援の有無」などを事前に確認するとミスマッチを防げます。
言語聴覚士は企業でも需要がありますか?
はい、教育系企業や医療機器メーカー、福祉サービス企業などで言語聴覚士の需要が増えています。
たとえば、
- 教材開発やトレーニングアプリの監修
- 製品の使用指導やサポート業務
- 子ども向け発達支援プログラムの開発
- 研修会の講師やマネジメント業務 など
こうした企業では、臨床現場での経験を「商品」や「サービス」の開発に活かす形で、専門性を発揮することができます。
特に最近は、ICTや福祉×ビジネスの分野でSTのニーズが拡大中です。
未経験でも採用されやすい就職先はありますか?
臨床未経験、またはブランクがある方でも、採用されやすい職場は以下のような特徴があります。
- 新人教育やOJTが整っている病院・老健施設
- 研修制度が充実しているリハビリテーション病院
- 放課後等デイサービス(比較的受け入れ体制が柔軟)
- 非常勤・パート勤務から始められる職場
また、「子育て後の復帰」や「他職種からの転職」に理解がある職場では、丁寧なサポートが受けられることもあります。
まずは自分の希望条件を明確にし、それに合う環境から少しずつ経験を積んでいくのが安心です。
自分に合った就職先を見つけるためにはどうすればいいですか?
まとめ|言語聴覚士の就職先一覧から自分に合った勤務先の特徴を理解しよう
言語聴覚士の就職先は、今や病院に限らず、介護施設・在宅リハ・教育現場・企業など多岐にわたる時代になっています。
そして、それぞれの現場には異なる役割や働き方、求められるスキルがあり、どこで働くかによってキャリアの方向性も大きく変わります。
病院では高度な医療リハビリを学び、介護施設では長期的なケアや多職種連携の経験を積むことができます。
小児分野に興味があるなら、保育園や特別支援学校、療育施設などが良い選択肢となるでしょう。
さらには、企業で開発や研修に携わるなど、臨床を越えたフィールドで活躍するSTも増えています。
就職先を選ぶ際は、
- 認定言語聴覚士の取得支援制度(学会費の補助、研修費支援など)
- 自分が関わりたい対象(年齢・疾患・生活環境)
- ライフスタイルに合った勤務形態
- スキルアップやキャリアパスの有無
- チーム医療や働く環境との相性
といったポイントを意識しながら、「自分にとって長く働きやすい場所はどこか?」を軸に考えていくことが大切です。
この記事を通じて、言語聴覚士の多様な働き方や、それぞれの職場の特徴が見えてきたのではないでしょうか。
今後の就職や転職を検討する際には、ぜひ今回の情報を参考にしながら、あなたらしいキャリアを築いていく一歩につなげてください。
言語聴覚士におすすめの
転職サイトランキング
トップ3「ミチビーク調べ」
参考記事:言語聴覚士(ST)におすすめの転職サイト・エージェント10選をランキング形式で一挙紹介!の記事はこちら
この記事の運営者情報
| メディア名 | ミチビーク |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社Method innovation |
| 会社ホームページ | https://www.method-innovation.co.jp/ |
| 所在地 |
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町3丁目6番11号 BADGE長堀BLD. 2階
|
| 代表取締役 | 清水 太一 |
| 設立 | 2016年11月1日 |
| 事業内容 | 集患支援事業 メディア運営事業 広告代理店事業 |
| お問い合わせ | michibi-Qのお問い合わせはこちら |