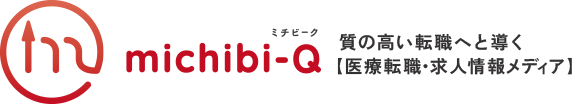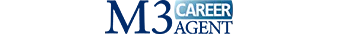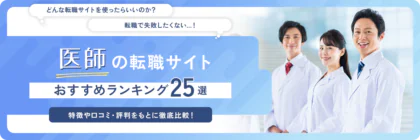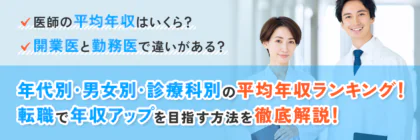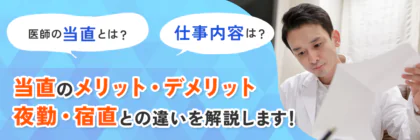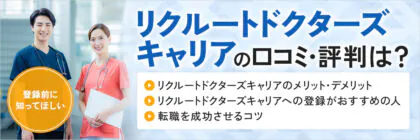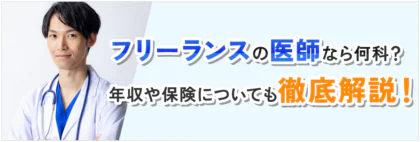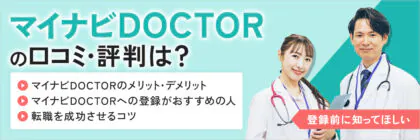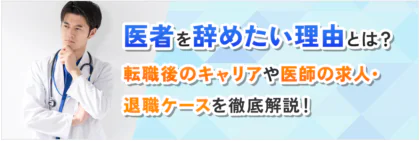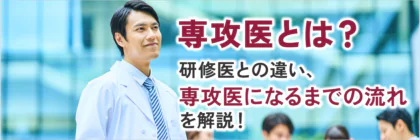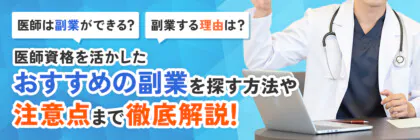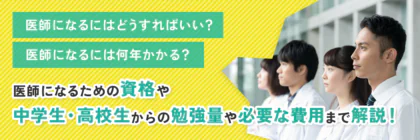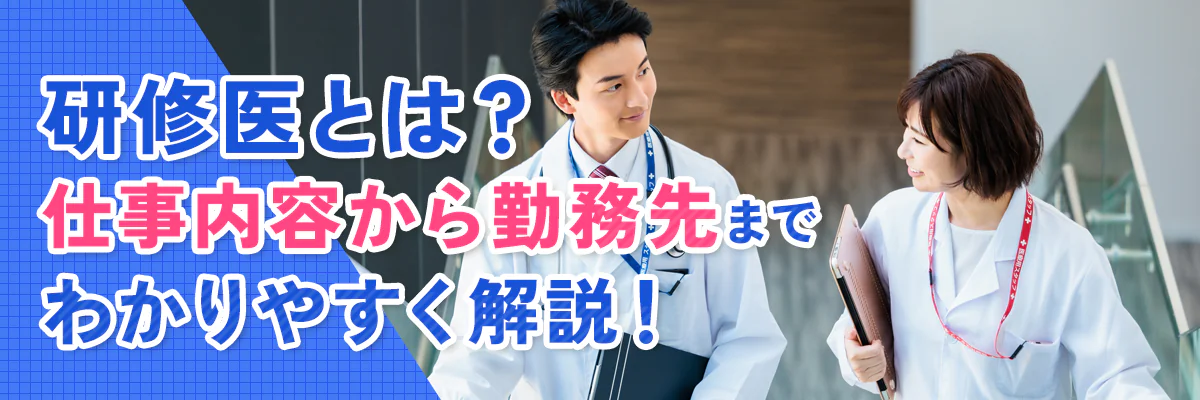
※当サイト(ミチビーク)はアフィリエイト広告を掲載しています。
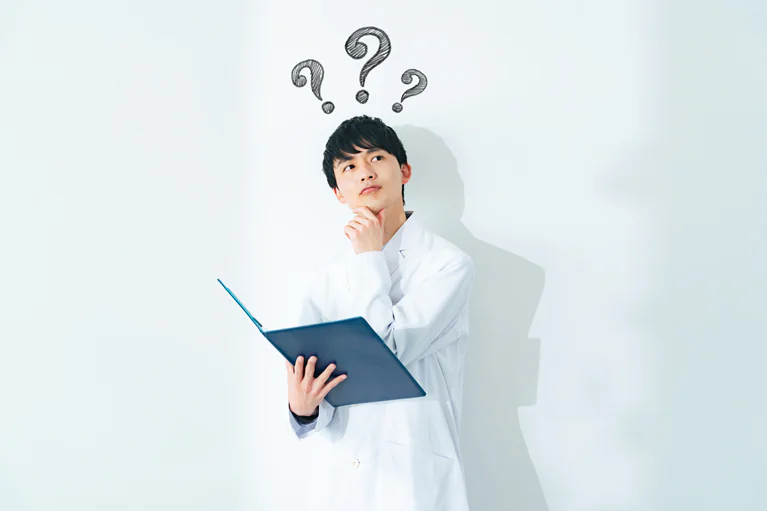 「研修医って、実際にはどんなことをしているの?」「医者とは何が違うの?」と疑問に思ったことはありませんか。
「研修医って、実際にはどんなことをしているの?」「医者とは何が違うの?」と疑問に思ったことはありませんか。
医師になるためには、国家試験に合格するだけでなく、病院での実地研修を経験する必要があります。この研修期間に働いている医師を「研修医」と呼びます。
この記事では、研修医の仕事内容や1日の流れ、勤務先、学生との違いなどを、大人の初心者の方にもわかるようにやさしく解説していきます。
研修医とはどんな仕事?仕事内容や役割をわかりやすく解説
研修医は、医師免許を取得したばかりの医師が、病院でさまざまな診療科を経験しながら、医師としての技術や判断力を身につけていく大切なステップにいます。
医師免許を取得後に行う実地研修
医師国家試験に合格した人は、すぐに独り立ちして診療を行うのではなく、最初の2年間は「研修医」として働くことが法律で決められています。これは、いきなり現場で一人前の医療を行うのは難しく、実際の患者さんと接しながら安全に経験を積んでいくためです。
研修医の期間は、知識だけでなく実践力を身につけるための重要な時間とされています。
指導医のもとで幅広い診療科を経験
研修医は、内科や外科、小児科、救急などの診療科を一定期間ずつまわりながら研修を受けます。これを「ローテーション研修」と呼び、さまざまな科を経験することで、医師としての視野を広げることができます。
どの診療科を専門にするかを決めるヒントにもなり、多くの学びを得られる貴重な期間です。
診察・処置の補助や記録業務を担当
研修医の業務には、患者の診察への同行や、注射・点滴の準備、診療の補助などがあります。また、診療の内容を電子カルテに記録することも大切な仕事です。
これらの業務を通じて、医療チームの一員としての責任感を持ちながら、少しずつ経験を積んでいきます。
初期臨床研修の目的と必修科目
初期臨床研修は、医師としての基礎を固めるための期間です。ここでは、診療の現場で幅広い症例を経験し、患者や家族とのコミュニケーション能力を養うことが重視されます。診療科ごとの知識や技術だけでなく、チーム医療の一員としての役割を理解することも重要です。
必修科目の例(厚生労働省の基準に基づく)
| 分野 | 主な経験内容 |
|---|---|
| 内科 | 高血圧、糖尿病、感染症など日常的な疾患の診断・治療 |
| 外科 | 手術前後の管理、創傷処置 |
| 小児科 | 小児の発熱・感染症対応、成長発達評価 |
| 産婦人科 | 妊婦健診、分娩補助 |
| 精神科 | うつ病、認知症、統合失調症などの初期対応 |
| 救急 | 外傷、心停止、重症感染症の初期治療 |
| 地域医療 | 診療所や小規模病院での総合診療 |
このカリキュラムに加えて、病院ごとに自由選択期間が設けられており、興味のある診療科を集中的に学ぶことも可能です。
後期研修との関係と専門分野への進み方
初期研修を修了すると、3年目からは後期研修、すなわち「専攻医」としての期間が始まります。この段階で、自身の専門分野を決定し、その領域で集中的に研修を積みます。
例えば、内科を選択すれば内科全般を3年間学んだ後、さらに循環器や消化器といった細分化された領域へ進むことも可能です。外科を選んだ場合は、手術技術を磨く日々が続きます。
後期研修は、将来の専門医資格取得のための必須期間であり、この時期の経験がその後の診療スタイルを大きく左右します。したがって、初期研修の段階から将来の進路を意識し、興味分野を試すことが重要です。
研修医の仕事内容とは?
1日の流れや具体的な業務内容
 研修医の1日は朝早くから始まり、外来や病棟での業務、当直など多くの仕事をこなす必要があります。ここでは、1日の主な流れについてわかりやすく紹介します。
研修医の1日は朝早くから始まり、外来や病棟での業務、当直など多くの仕事をこなす必要があります。ここでは、1日の主な流れについてわかりやすく紹介します。
朝は申し送りやカンファレンスから始まる
研修医の朝は、前日の夜間の患者の情報をチームで共有する「申し送り」からスタートします。その後は、患者の治療方針や検査の結果を話し合う「カンファレンス」と呼ばれるミーティングがあります。
この時間を通して、1日の診療の流れを確認し、医師同士の情報をそろえることができます。
日中は外来・病棟業務や処置を担当する
午前中から午後にかけては、外来患者の診察補助や、入院患者の経過観察、必要な検査の準備や処置を行います。病棟では、患者の体調の変化に気づき、看護師や上級医に報告することも大切な仕事の一つです。
日中の業務は、実際の診療に深く関わる時間でもあり、実践的なスキルを磨くチャンスでもあります。
夜は当直や急変対応に備えることもある
研修医には、夜間の当直が割り当てられることがあります。当直中は救急外来の対応や、入院患者の急変に備えて病院に待機します。大きな病院では、救急車で運ばれてくる患者の初期対応に関わることもあります。
夜間の業務は大変ですが、対応力や判断力を鍛える貴重な機会となります。
電子カルテ入力や診療記録の作成も重要な仕事
診療後には、患者の症状や治療内容などを電子カルテに記録します。これらの記録は、ほかの医療スタッフとの情報共有や、後日の診療にとって非常に重要なものです。
記録は手間がかかりますが、医師としての信頼につながる大切な業務のひとつです。
研修医の勤務先とは?
どんな場所で働いているのか
 研修医は、国が指定した「臨床研修指定病院」で働くことになっています。
研修医は、国が指定した「臨床研修指定病院」で働くことになっています。これには大学病院だけでなく、市中病院や地域の中核病院など、さまざまな医療機関が含まれます。
大学病院や市中病院などの臨床研修指定病院で働く
大学病院では、専門的な治療や最先端の医療技術を学ぶことができます。一方で、市中病院ではより実践的な診療を経験できることが多く、日常的に起きる病気やけがに対応する力がつきやすい環境です。
それぞれの病院に特徴があるため、自分の学びたいスタイルに合った場所を選ぶことが大切です。
大学病院と市中病院の特徴と違い
研修先には大きく分けて大学病院と市中病院があります。
大学病院は最先端医療や研究に触れる機会が豊富で、専門性の高い症例や珍しい病気を経験できます。しかし、研修医の人数が多く、手技の機会が限られる場合もあります。
一方、市中病院は地域医療の最前線として、日常的に多くの患者を診る機会があり、救急対応や一般診療のスキルが磨かれます。手技の経験が多いのも特徴です。
| 項目 | 大学病院 | 市中病院 |
|---|---|---|
| 労働時間 | 専門性の高い症例、希少疾患 | 一般的な症例、救急外来が多い |
| 教育体制 | 研究・学会発表の機会が豊富 | 実践的な手技が多い |
| 人員 | 研修医が多く競争が激しい | 少人数で密な指導 |
| キャリア | 大学医局とのつながりが強い | 地域医療や市中病院での勤務に有利 |
どちらが優れているというわけではなく、自分の将来像や学びたいことに合わせて選ぶべきです。
地域の中核病院での勤務も多い
都市部だけでなく、地方の中規模病院で研修を行う研修医も増えています。地域の患者と密接に関わることで、医療の本質やコミュニケーションの大切さを学ぶことができます。
また、指導医との距離が近く、手厚いサポートを受けられる環境も魅力の一つです。
救急病院での研修もカリキュラムに含まれている
すべての研修医は、救急科での研修を一定期間行う必要があります。これは、急な病気やけがに対応する力を身につけるためで、実践的で緊張感のある場面が多く、研修の中でも特に重要な経験となります。
緊急性の高い患者を前にしても冷静に対応する力が求められますが、その分だけ得られる成長も大きい研修です。
勤務先(研修先)の選び方とポイント
 研修先の病院選びは、医師としてのキャリアの方向性や診療スタイルを決定づける極めて重要なステップです。初期臨床研修の2年間は、あらゆる診療科を回りながら総合的な診療能力を培う期間であり、この経験が後の後期研修や専門医資格取得の基礎となります。
研修先の病院選びは、医師としてのキャリアの方向性や診療スタイルを決定づける極めて重要なステップです。初期臨床研修の2年間は、あらゆる診療科を回りながら総合的な診療能力を培う期間であり、この経験が後の後期研修や専門医資格取得の基礎となります。
選び方の基準は多岐にわたります。研修プログラムの自由度、病院の種類や規模、症例の多様性、指導体制、給与や福利厚生、さらには病院の雰囲気や立地条件まで、全てが研修医生活の満足度に影響します。加えて、病院見学や合同説明会を通じた事前の情報収集も欠かせません。この章では、それらのポイントを一つずつ具体的に解説していきます。
研修プログラムの選択基準と自由選択期間
病院ごとに研修プログラムの内容は大きく異なります。厚生労働省が定める必修科目は全国共通ですが、必修以外にどの診療科をどれだけ回れるかは病院次第です。
「自由選択期間」が長い病院では、自分の興味ある診療科を重点的に学ぶことができ、将来の進路を決めやすくなります。一方で、自由度が低い場合は、多くの診療科をまんべんなく経験できますが、自分の専門志向を早く固めたい人には物足りないこともあります。
自由選択期間の長さ比較(例)
| 病院A | 自由選択期間 6か月 | 特定科を深く学べる |
|---|---|---|
| 病院B | 自由選択期間 2か月 | 幅広い科を経験できる |
選択の際には、自分が「幅広く経験したいタイプ」か「特定分野を早く深めたいタイプ」かを事前に明確にすることが重要です。
指導体制と研修医の人数バランス
指導医の数や質は研修生活の質を大きく左右します。経験豊富で教えることに熱心な指導医が多い環境では、質問や相談がしやすく、成長も早まります。また、同期の研修医の人数も重要です。
人数が多すぎると手技のチャンスを得るのが難しくなることもありますが、逆に少なすぎると相談相手が少なく孤立しがちです。理想的なのは、適度な人数で協力し合える雰囲気のある病院です。
病院見学と情報収集
病院選びでは、公式サイトやパンフレットだけではわからない情報が重要です。実際に見学に行くことで、病院の雰囲気や研修医の働き方を肌で感じられます。また、合同説明会やセミナーに参加すれば、多くの病院を比較できます。
特に、先輩医師や同じ大学出身の研修医からの直接の話は、ネットや資料では得られないリアルな情報源になります。勤務の実情や当直の忙しさ、指導体制の雰囲気などを事前に知ることで、ミスマッチを防ぐことができます。
病院選びのチェック項目例
- 自由選択期間の長さは自分に合っているか
- 興味のある診療科を経験できるか
- 指導医の人数・指導の熱心さ
- 症例の種類と数
- 給与・福利厚生
- 病院の立地と生活環境
研修医は何年続く?
仕事内容と勤務先の変化も紹介
 研修医として働く期間には段階があり、大きく分けて「初期研修」と「後期研修(専門研修)」の2つがあります。
研修医として働く期間には段階があり、大きく分けて「初期研修」と「後期研修(専門研修)」の2つがあります。
多くの研修医は、まず2年間の初期研修を行い、その後は専門分野に進んでさらに学びを深めていきます。
初期研修は基本的に2年間で終了
日本では、医師免許を取得したすべての医師が、原則として2年間の初期研修を受けることが法律で定められています。この期間中は、内科・外科・救急医療・地域医療などのさまざまな分野を経験します。
この2年間で、基礎的な診療技術や患者対応のスキルを学び、どの専門科に進むかの判断材料を集めることができます。
2年目からは希望科に近い研修ができるようになる
初期研修の1年目は共通の研修内容が多いですが、2年目になると自分の興味がある診療科を多く回ることができるようになります。たとえば外科に興味があれば外科の研修期間を長めにするなど、より専門的な経験を積むことが可能です。
この時期に得た経験が、後の専門研修や医師としての進路選びに大きく影響してきます。
後期研修(専門研修)に進むと勤務先が変わることもある
初期研修を終えると、希望する診療科で「専門医」を目指す後期研修に進みます。この後期研修は通常3年から5年ほど続き、診療の中心的な役割を担うことも増えてきます。
この段階では勤務先が変わるケースもあり、大学病院に戻ったり、専門の診療科が強い病院に移ったりして、より実践的で専門的な研修が行われます。
研修医マッチングと採用までの
流れ
 研修医として働くためには、全国規模で行われる医師臨床研修マッチング制度を通じて研修先病院に採用される必要があります。これは、医学生と病院の双方が希望を出し合い、コンピューターでマッチングさせる仕組みです。
研修医として働くためには、全国規模で行われる医師臨床研修マッチング制度を通じて研修先病院に採用される必要があります。これは、医学生と病院の双方が希望を出し合い、コンピューターでマッチングさせる仕組みです。
就職活動に似ていますが、希望順位の付け方やスケジュールの把握が非常に重要で、準備不足は希望病院への進路を大きく左右します。この章では、制度の概要、採用までの時系列、そして希望通りの病院に進むための面接・エントリー対策を詳しく解説します。
マッチング制度の概要とエントリー方法
医師臨床研修マッチング制度は、全国の医学生が登録し、各病院の採用枠に基づいて配属先を決める仕組みです。
エントリーは専用サイトから行い、志望する病院を希望順位順に登録します。一方、病院側も面接や書類選考を経て、受け入れたい候補者を順位付けします。
最終的に、両者の順位を照合して最も高いマッチング率になる組み合わせが決まります。
制度の特徴
- 希望順位は複数登録可能(上限あり)
- 病院によって応募条件や書類の種類が異なる
- 早い段階で病院見学や面接を行う場合もある
採用までのスケジュールと流れ
採用までの大まかな流れは以下のようになります。
【5年生】
夏休みに病院見学を開始
【6年生】
春休みに本命の病院見学
4〜6月 選考試験を受験
6〜8月 マッチング参加エントリー受付
8〜10月 面接試験
9月中旬 ~10月中旬 希望順位登録
10月末 マッチング結果発表
翌年4月 研修開始
このスケジュールの中で、病院見学や面接は単なる形式ではなく、評価対象になることが多いため、事前準備が重要です。
希望の病院に合格するための面接対策
面接では、医師としての姿勢や人柄、チーム医療への適応力が重視されます。特に「なぜこの病院を選んだのか」という志望動機は必ず聞かれます。
準備のポイントは以下の通りです。
- 志望動機を病院ごとに具体化する
(例:「救急外来の豊富な症例に魅力を感じた」など) - 学生時代の経験を整理する
(臨床実習で印象に残った症例や学び) - 自己PRは短く端的に
(長すぎると印象が薄れる)
また、集団面接では協調性、個別面接では誠実さや論理的な説明力が見られるため、それぞれに合わせた練習が必要です。
マッチング成功のためのチェック項目
- 病院見学で好印象を与えたか
- 志望動機を明確に言えるか
- 面接練習を複数回行ったか
- 提出書類に誤字・脱字がないか
研修医の給料と勤務条件
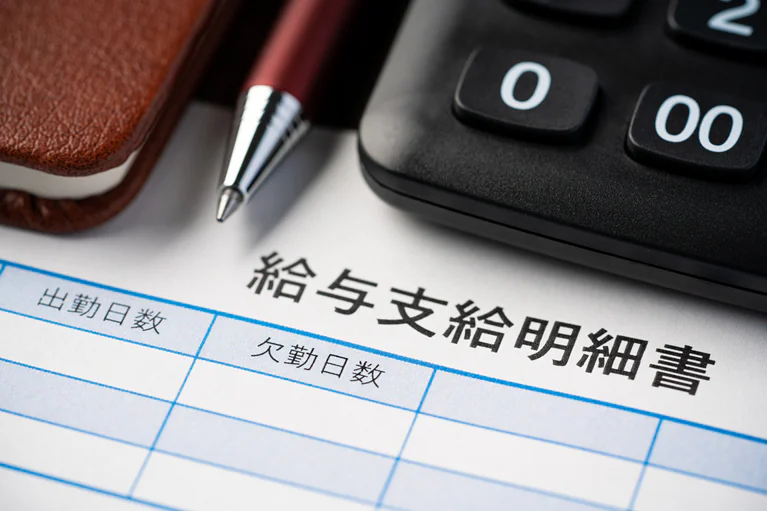 研修医の給与や勤務条件は、研修先によって大きく異なります。都市部の大学病院では年収が低めな傾向があり、地方の市中病院では比較的高額なケースも少なくありません。また、給料の額だけでなく、勤務時間、当直回数、福利厚生など、生活に直結する条件も重要です。この章では、年収の目安から当直手当の仕組み、福利厚生の種類まで、研修医生活を支える実際の条件を詳しく解説します。
研修医の給与や勤務条件は、研修先によって大きく異なります。都市部の大学病院では年収が低めな傾向があり、地方の市中病院では比較的高額なケースも少なくありません。また、給料の額だけでなく、勤務時間、当直回数、福利厚生など、生活に直結する条件も重要です。この章では、年収の目安から当直手当の仕組み、福利厚生の種類まで、研修医生活を支える実際の条件を詳しく解説します。
年収の目安と都市部・地方の違い
一般的な研修医の年収は、300万円〜500万円が相場です。都市部の大学病院では年収300万円前後が多く、地方の市中病院では400万円〜600万円、場合によっては1,000万円を超えるケースもあります。
高額な年収の背景には、当直の多さや人手不足などの事情がある場合が多く、収入だけを基準にすると労働負担が大きくなることもあります。
| 地域・病院タイプ | 年収目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 都市部・大学病院 | 約300〜350万円 | 教育環境充実、手技機会は少なめ |
| 都市部・市中病院 | 約350〜450万円 | バランス型、症例数が豊富 |
| 地方・市中病院 | 約450〜600万円 | 実践機会多い、当直多め |
| 高待遇病院 | 約700万円〜1,000万円超 | 当直頻度・負担大きい |
当直や時間外勤務と手当の関係
研修医の給料の中で変動が大きいのが当直手当です。
当直は夜間や休日に病院で待機し、急患対応や入院患者の管理を行います。当直1回あたりの手当は、都市部で10,000〜20,000円、地方で20,000〜30,000円程度が一般的です。
例えば、当直を月4回行う場合、手当だけで月に8〜12万円程度の上乗せが期待できます。
ただし、当直明けの勤務がそのまま続く「残業当直」の場合、身体的な負担は大きくなります。
福利厚生や住宅手当の実態
給与以外に生活を支えるのが福利厚生です。住宅手当や病院の寮が整備されている場合、生活費を大幅に抑えられます。
特に地方病院では、家賃無料の病院寮や、月数千円の負担で住める施設があることも珍しくありません。
福利厚生の例
- 住宅手当(家賃の半額〜全額補助)
- 病院寮(格安または無料)
- 食堂利用の補助(1食200〜300円)
- 学会参加費や交通費の補助
- 健康診断や予防接種の無料実施
こうした条件は募集要項に明記されないことも多いため、病院見学や先輩へのヒアリングで確認することが重要です。
例:年収シミュレーション(都市部大学病院・地方市中病院)
| 項目 | 都市部 大学病院 |
地方 市中病院 |
|---|---|---|
| 基本給 | 約300万円 | 約420万円 |
| 当直手当 (月4回) |
約48万円 | 約96万円 |
| 年収合計 | 約348万円 | 約516万円 |
よくある質問|研修医とは?
仕事内容や勤務先の疑問を解決
研修医は医師だけど独り立ちはしていないのですか?
はい、その通りです。研修医は医師としての資格を持っていますが、まだ一人で患者を診る立場ではなく、必ず指導医の管理のもとで診療にあたります。
患者対応や処置も行いますが、すべての判断は上級医のサポートがあることが前提です。
研修医の給料はどれくらいですか?
研修医の給与は病院によって異なりますが、月収でおおむね25万円〜35万円程度が一般的です。これに加えて、当直手当や交通費、住居補助などの福利厚生がある病院もあります。
金額だけを見ると高くはありませんが、学びながら働くという性質を考えると、妥当な範囲と言えるでしょう。
女性の研修医も多いのでしょうか?
はい、最近では女性の研修医も増えており、医学部の学生全体の約4割が女性というデータもあります。
病院によっては育児支援や柔軟な勤務制度を導入しているところもあり、ライフスタイルに合わせた働き方ができるような環境が整ってきています。
当直や残業はどのくらいありますか?
研修医は忙しい仕事ですが、過度な長時間労働を避けるよう配慮されている病院も増えています。当直は月に数回程度あり、夜間も病院に待機して急患の対応にあたります。
また、日中の業務が終わった後にもカルテ記録や症例の勉強があることから、残業が発生することもありますが、しっかりと休める体制を整えている病院も多くなってきています。
研修医と医学生の違いは何ですか?
研修医は医師免許を取得し、病院に常勤で勤務しながら診療に従事する医師です。一方、医学生は大学の医学部に在籍し、講義や実習で医学を学ぶ段階であり、診療の直接的な責任はありません。
専攻医と専門医の違いはどう理解すればいいですか?
専攻医は後期研修期間中の医師で、特定分野の研修プログラムを履修中です。専門医は、専攻医期間を修了し、学会や専門医機構が定める資格試験に合格して認定を受けた医師です。
参考記事:専攻医とは?研修医との違い、専攻医になるまでの流れを解説!
研修先の病院はどのように選べばよいですか?
研修プログラムの自由度、必修科目以外の選択肢、指導医の質、症例数、給与、福利厚生、立地条件などを総合的に比較します。病院見学や説明会、先輩医師からの情報収集も重要です。
マッチング制度で第一希望の病院に入るためのコツはありますか?
早期の病院見学で印象を良くし、志望動機を明確かつ具体的に説明できるよう準備します。また、面接練習を複数回行い、提出書類の誤字脱字をなくすことも大切です。
まとめ|研修医とは何かを仕事内容や勤務先からやさしく解説
研修医は、医師免許を取得したばかりの若手医師が、現場で学びながら成長していく大切な時期にあります。診察の補助や記録の作成、当直など多くの実務に携わりながら、医療現場での経験を積んでいきます。
研修医は医師として成長するための第一歩
大学での勉強や国家試験を終えた後、初めて現場に立って学ぶのが研修医の期間です。この2年間で、診療の基礎から患者対応まで、幅広く医師としての力をつけていきます。
病院で実際の診療に関わりながら学ぶのが特徴
教科書や講義では学べないことを、現場で実際に患者と接しながら体験し、判断力や責任感、そして医療チームとの連携の大切さを学んでいきます。
知識だけではなく、人としての成長も求められる貴重な期間です。
2年間で多くの経験を積み、次のステップに進む
初期研修の2年間を経て、多くの研修医は専門分野に進み、さらなる技術や知識を深めていきます。研修医の時期に積んだ経験は、その後の医師人生を支える大きな力となります。
ミチビークは、これから医師を目指す方や、医療業界に関心がある方にとって、研修医という存在は医師としての始まりを象徴する、非常に大切な役割であることを理解してもらうために、未来の医療を担うあなたを応援していきます。
医師におすすめ転職サイト「ミチビーク調べ」
参考記事:医師におすすめの転職サイト2024年ランキング【厳選25社】徹底比較|選び方は?評判は?
この記事の運営者情報
| メディア名 | ミチビーク |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社Method innovation |
| 会社ホームページ | https://www.method-innovation.co.jp/ |
| 所在地 |
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町3丁目6番11号 BADGE長堀BLD. 2階
|
| 代表取締役 | 清水 太一 |
| 設立 | 2016年11月1日 |
| 事業内容 | 集患支援事業 メディア運営事業 広告代理店事業 |
| お問い合わせ | michibi-Qのお問い合わせはこちら |